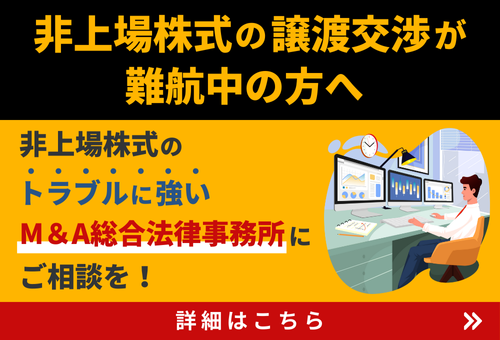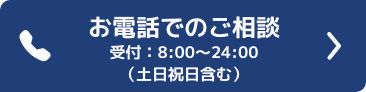非上場株式の譲渡適正価格はいくら?少数株主が適正価格で譲渡(売却)する方法を解説

非上場株式を手放したいと思っても、「いくらで譲渡するのが適正なのか」が分からず、足踏みしている方は少なくありません。
上場株式のように市場価格が表示されているわけではなく、会社やオーナー、他の株主から「この金額で買い取ります」と提示されても、それが高いのか安いのか判断しづらいのが非上場株式の難しさです。
とくに少数株主の立場では、会社の内部事情や将来の見通しに関する情報も限られがちで、「この条件を飲まないと関係が悪くなるのではないか」「税金のこともよく分からないままサインしてしまって大丈夫だろうか」と、不安を抱えたまま話が進んでしまうこともあります。
本記事では、非上場株式を譲渡する際の適正価格というテーマについて、ご自身の状況を整理できるように、価格の考え方・代表的な評価方法のイメージ・譲渡先ごとのポイント・交渉の進め方・最低限押さえたい税金と法律の注意点を解説します。
そのうえで、どのような場面で専門家に相談すべきかについても触れますので、「このまま相手の言い値でいいのか」と感じている方は、判断材料としてお役立てください。
非上場株式の譲渡の適正価格とは
非上場株式を手放したい少数株主の方が最初に直面するのは、「株式をいくらで譲渡するのが妥当なのか」という問題です。上場株式のように市場で株価が表示されているわけではないため、相手から提示された金額が適正なのか、安く買い取られようとしているのかが分かりにくい状況になりがちです。
非上場株式とは、証券取引所に上場しておらず、市場で自由に売買されていない株式を指します。株式譲渡の相手は、会社自身、オーナー経営者個人、他の株主、取引関係のある第三者など、会社と一定の関係を持つ相手方になることが多く、取引のたびに個別に条件を決めることが一般的です。このため、同じ会社の株式であっても、誰が誰に売るのかによって株式価格が変わることがあります。
ここでいう非上場株式の「適正価格」とは、会社法上の株式買取請求において裁判所が決定する「公正な価格」(会社法785条・786条)や、相続税・贈与税の計算のために財産評価基本通達に基づいて求められる「時価」といった法令上の概念も踏まえつつ、当事者双方が一定の合理性を認められる価格水準を指します。
これらの法令上の株式価格と実際の取引価格が完全に一致するとは限りませんが、複数の考え方を組み合わせて、少なくとも一方当事者に過度な不利益が生じない範囲を見極めていくことが重要です。
少数株主が悩みやすい状況
少数株主が非上場株式の譲渡を検討するきっかけには、いくつか共通したパターンがあります。ここでは代表的な場面を整理します。
退職や役職変更に伴って株式を手放したい場合
勤務先の従業員持株会に参加していたが退職することになり、保有している株式を処分したいというケースがあります。また、かつて役員や創業メンバーだったものの、現在は経営から離れており、持ち株だけが残っている場合もあります。このような場合、会社やオーナー、他の株主から「この価格で買い取りたい」と提案されることが多く、その妥当性が問題になります。
相続や家族関係の変化をきっかけに整理したい場合
親族から非上場株式を相続したものの、その会社の経営に関与しておらず、今後も関わる予定がないというケースも少なくありません。株式を持ち続ける意味が薄いと感じ、現金化を検討する中で、「どこに、いくらで売るべきか」が課題となります。
経営方針や人間関係の対立を背景とする場合
他の株主や経営陣との考え方の違い、人間関係の悪化などを背景に、持ち株を整理したいという相談もあります。この場合、感情的な対立があることも多く、価格だけでなく交渉の進め方を慎重に考える必要があります。
非上場株式の適切な譲渡価格が難しいと言われる理由
非上場株式を適切な価格で譲渡することが難しいと言われる背景には、いくつかの構造的な要因があります。主なポイントを整理します。
市場価格が存在しない
上場株式であれば、証券取引所で日々取引されており、その時点の市場価格を前提に話を進めることができます。これに対し、非上場株式には公開された相場がありません。取引のたびに当事者が価格を決める必要があるため、「客観的な基準」が見えにくくなります。
情報量の差が交渉力の差になりやすい
会社側は業績、資産、将来の事業計画などについて詳細な情報を持っています。一方で、少数株主は決算書や事業の見通しを十分に知らされていないこともあります。この情報の差がそのまま交渉力の差となり、提示された株式の価格に疑問を感じても、反論の材料を用意しにくい状況になりがちです。
株式の評価の前提によって価格に幅が出る
会社の利益に着目するのか、保有している資産に着目するのか、配当や将来のリターンに着目するのかによって、算定される価格は変わります。DCF法のように将来のキャッシュフローを重視する方法もあれば、純資産や配当を基準にする方法もあります。さらに、税金計算のための評価額と、当事者間で合意する取引価格が一致しないこともあり、株式の価格に「幅」が生じやすいのが現状です。
非上場株式の売却でお困りではありませんか?
非上場株式のトラブルならご相談ください
少数株主と非上場株式の譲渡や売却が難しい理由
非上場株式を持つ少数株主の多くは、「譲渡や売却をしたいのに、どう動けばいいか分からない」という壁にぶつかります。
その背景には、上場株式にはない「売りにくさ」の構造がいくつかあります。ここでは、その特徴を整理して、なぜ少数株主が不利な立場になりやすいのかを確認していきます。
上場株式と違い市場価格がない非上場株式
上場株と非上場株の大きな違いは、「今この瞬間の値段」が客観的に分かるかどうかです。
上場株式には常に「相場」がある
上場株式であれば、証券取引所で日々売買されており、ニュースや証券会社のアプリを見れば、その銘柄の株価がすぐ分かります。
売りたいと思ったときは、その時点の市場価格を基準に、「いくらで売れそうか」をイメージしやすくなっています。
非上場株式には公開された価格がない
これに対して、非上場株式には、証券取引所のような市場がありません。
「非上場株式 譲渡 適正価格」と検索しても、自分が持っている会社の株価が具体的に出てくることはありません。
実際の取引では、「1株あたり○円で買い取りたい」「出資したときと同じ金額でどうか」 といった形で、相手から金額を提示されることが多くなりますが、その数字が妥当かどうかを判断する基準が見えにくいのが現状です。
情報の非対称性と交渉力の差
非上場株式の売却では、「情報をどれだけ持っているか」が、そのまま交渉力の差になりやすいという問題があります。
会社側は業績や将来計画を詳しく知っている
会社やオーナーは、決算数字、保有している資産の内容、将来の事業計画などを詳細に把握しています。今後の利益が増えそうなのか、逆に厳しくなりそうなのか、内部の状況を前提に「いくらなら割に合うか」を考えることができます。
少数株主は判断材料が限られやすい
一方で、少数株主は、決算書を受け取っていなかったり、今後の事業方針を聞かされていない といった状況に置かれていることがあります。このような場合、 「なぜその価格なのか」「他の計算方法だといくらくらいになるのか」を検証しにくく、提示された価格を受け入れるかどうかを判断しづらくなります。
情報を求めること自体を遠慮してしまうこともある
さらに、「会社に疑いをかけていると思われたくない」「関係が悪くなるのが怖い」といった心理から、詳しい資料を求めたり、価格の根拠を尋ねる といった行動を控えてしまうことも少なくありません。
このような心理的ハードルも、少数株主を弱い立場にしてしまう一因になります。
譲渡制限株式・会社の承認制の影響
多くの中小の非上場会社は、会社法上の譲渡制限株式(いわゆる非公開会社)として、定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定めています。この譲渡制限の有無や内容が、少数株主の「売りにくさ」を大きく左右します。
定款で「株式の譲渡には承認が必要」とされているケース
譲渡制限株式を発行する会社では、定款で「株式を譲渡するには取締役会または株主総会の承認が必要である」と定めていることが一般的です。
このルールがあると、株主が自由に第三者へ株式を譲渡することはできず、会社の承認がなければその第三者は株主としての地位を取得したものとして株主名簿に記載してもらえません。売買契約そのものは当事者間で成立し得ますが、会社が承認しない限り名義書換がされず、第三者は会社に対して株主としての権利を行使できないという状況になり得ます。
なお、譲渡制限株式について会社が第三者への譲渡を承認しない場合、会社法は会社または会社が指定する買取人に株式を買い取らせる制度や、その買取価格について裁判所に売買価格の決定を申し立てる手続を定めています。
ただし、これらの手続を適切に利用するには専門的な検討が必要になるため、少数株主だけで対応するのは容易ではありません。
承認手続きやルールを確認することの重要性
このような事情があるため、
- 定款にどのような株式の譲渡制限があるか
- 取締役会や株主総会の譲渡承認が必要か
- 過去にどのような価格で株式が取引されてきたか
を把握することは、少数株主にとって重要な下調べになります。
こうしたルールを知らないまま話を進めてしまうと、 「せっかく譲渡先を見つけたのに承認されず、時間だけが過ぎてしまう」といった事態にもつながりかねません。
このように、非上場株式を持つ少数株主は、市場価格がなく、情報が不足しがちで譲渡制限で相手を選びにくいというハンデを負いやすい立場にあります。
非上場株式を譲渡するときの手続きの流れ
非上場株式の譲渡は、「買い手が見つかれば終わり」ではありません。多くの非上場会社では株式に譲渡制限が付いており、会社の承認を経ないと名義を変えられないことがあります。
手続きを飛ばしてしまうと、代金の受け渡しだけが先に進み、あとで「株主として扱ってもらえない」「名義が戻らない」といった問題につながることもあります。
① まずは譲渡制限と「承認する機関」を確認する
最初にやるべきことは、その株式が自由に譲渡できるのか、それとも会社の承認が必要なのかを確かめることです。
譲渡制限の有無は定款で定められていることが多く、登記事項証明書(登記簿)にも「株式の譲渡制限に関する規定」が載っています。また、承認する機関が取締役会なのか株主総会なのかは会社によって異なります。
あわせて、株券発行会社かどうか(株券を出している会社かどうか)も確認しておくと、その後の引渡し手続きで迷いにくくなります。
② 譲渡承認請求を出し、会社から通知を受ける
譲渡制限がある場合は、譲渡人(売り手)または譲受人(買い手)が、会社に対して「譲渡の承認」を求めることになります。
会社は原則として請求日から一定期間内に承認・不承認を通知する必要があり、期限内に通知がないと承認された扱いになることがあります(会社法145条)。
会社が承認しない場合でも、会社や会社が指定する買い手が株式を買い取る制度や、価格が折り合わないときに裁判所に価格決定を求める制度が用意されているため、「不承認=何もできない」で終わるとは限りません。
③ 代金決済と名義書換まで完了させる
会社の承認が得られたら、株式譲渡契約書に基づいて代金を支払い、株券発行会社であれば株券の引渡しを行います。そのうえで、会社に対して株主名簿の名義書換(株主名簿への記載)を求めます。
非上場株式では、この名義書換ができていないことが後日のトラブル原因になりやすいため、契約書の締結や代金の支払と同じくらい重要な手続きです。
非上場株式の譲渡価格を考えるときの3つの視点
非上場株式の「適正価格」を考えるときに、最初から細かい計算式や専門用語に踏み込む必要はありません。まずは、どんな角度から会社の価値を見ていくかという「視点」を押さえておくと、自分が置かれている状況を整理しやすくなります。
ここでは、少数株主の方にもイメージしやすいように、次の3つの視点に分けて説明します。
- 会社の利益・キャッシュフローから見る視点(インカムの視点)
- 純資産・財産から見る視点(ネットアセットの視点)
- 配当や将来のリターンから見る視点(リターンの視点)
① 会社の利益・キャッシュフローから見る(インカムの視点)
この視点は、「この会社はどれくらいお金を生み出せるのか」に着目する考え方です。
利益やキャッシュフローに着目する理由
株式の価値は、最終的にはその会社が将来生み出す利益やキャッシュフロー(現金収支)と深く結びついています。例えば、毎年安定して利益を上げている会社と、赤字が続いている会社では、同じ資産を持っていたとしても評価は違ってきます。
このような発想を、もう少し踏み込んで形にしたものが、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)と呼ばれる評価方法です。
DCF法のイメージ
DCF法を、あえて簡単に表現すると次のようなイメージです。
- 今後数年間、その会社が生み出すと見込まれるキャッシュフローを予測する
- その将来のお金を「今の価値に割り引いて」合計する
- その総額を会社全体の価値とみなす
たとえば、今後も売上・利益が伸びていきそうな成長企業であれば、将来のキャッシュフローは大きくなります。その結果、DCF法で評価すると、現在の利益だけを見た場合よりも高い価値が出ることがあります。
この視点が向いている会社・少数株主に有利な場面
インカムの視点は、次のようなケースで特に意味を持ちます。
- すでに一定の利益水準を維持している、または今後の成長が期待できる会社
- 資産はそれほど大きくなくても、事業そのものの収益力が高い会社
- 将来の利益を重視したい少数株主が、「今の利益だけを理由に低く評価されること」に違和感を持っている場面
一方で、事業の将来性が読みにくい会社や、利益が安定していない会社では、将来のキャッシュフローの予測が難しくなります。そのような場合は、次に説明する「純資産の視点」など、別の角度からの見方も併せて検討することが大切です。
② 純資産・財産から見る(ネットアセットの視点)
この視点は、「この会社には今どれくらいの財産が残っているか」に着目する考え方です。
純資産とは何か
会社の貸借対照表(バランスシート)には、資産(現金、預金、不動産、機械設備、有価証券など)、負債(借入金、買掛金などの支払義務)が記載されています。
純資産とは、簡単にいえば「資産 − 負債 = 純資産」という形で計算される残りの部分です。
純資産ベースで株価を考えるイメージ
純資産の総額を、発行されている株式数で割ると、「1株あたりの純資産」の目安が分かります。
たとえば、
- 純資産:1億円
- 発行株式数:1万株
であれば、単純計算上は
1億円 ÷ 1万株 = 1株あたり1万円
というイメージになります。
もちろん、実際には簿価と時価が違う資産(不動産など)があったり、含み損や含み益があったりしますので、調整が必要になることもありますが、「会社をきれいに清算したら、1株あたりどのくらい残るのか」という感覚に近い見方です。
この視点が向いている会社・少数株主に有利な場面
純資産の視点は、次のような場合に特に意味を持ちます。
- 利益はそれほど大きくないが、不動産や有価証券などの資産を多く保有している会社
- 会社が将来どれだけ利益を出せるかは不透明だが、現時点での財産価値はある程度把握できる会社
- 「利益が出ていないから価値は低い」と説明されているが、資産の内容を考えると納得できない少数株主
このような場面では、「利益だけ」でなく「財産の側面」からも会社の価値を見直すことで、提示された価格が妥当かどうかを考えやすくなります。
③ 配当や将来のリターンから見る(リターンの視点)
3つ目の視点は、「この株式を持っていると、将来どんなリターンが期待できるか」に着目する考え方です。
配当金に着目する見方
非上場株式であっても、会社が利益を上げていれば、株主に配当金を支払っている場合があります。
その場合、1株あたり毎年どのくらいの配当が出ているのか?今後も同じように配当が続きそうか?といった点を確認することで、「この株を持っている価値」をイメージしやすくなります。
配当金を基準に株価を考える方法として、配当還元法という考え方があります。これは、将来見込まれる配当金の総額などを基に、「その配当を得るための株価はいくらか」を逆算するイメージです。
ここで説明している配当還元法は、ファイナンスの一般的な考え方としての配当割引モデルのイメージであり、相続税や贈与税の評価で財産評価基本通達に基づいて用いられる「配当還元方式」とは必ずしも同じものではありません。
配当が少ない会社・無配の会社の場合
一方で、配当をほとんど出していない会社や、成長投資を優先して無配としている会社も多くあります。このような場合、配当の情報だけを基準に株価を考えると、実態に合わない低い評価になってしまうことがあります。
そのため、配当が少ない会社では、配当だけでなく、利益や純資産の情報も併せて見るという点に注意が必要です。
「額面」「取得価額」と適正価格の違い
非上場株式の取引では、相手から「額面どおりで買い取りましょう」「出資したときの金額でどうでしょう」といった提案を受けることがあります。一見すると分かりやすい条件ですが、額面や取得価額と、現在の適正価格は別のものである点に注意が必要です。
額面とは何か?
額面(額面金額)とは、かつて会社が額面株式を発行するときに株券に記載していた「1株あたりの名目上の金額」を指します。2001年の商法改正により額面株式制度は廃止され、現在発行される株式は原則としてすべて無額面株式とされています。
そのため、古い株券などに「1株の額面が5万円」といった記載が残っていても、その額面金額が現在の株式価値や税務上の評価額を直接意味するわけではなく、現在の適正価格とは切り離して考える必要があります。
取得価額と現在の価値は一致しない
また、株式を取得した当時の金額(取得価額)も、会社の規模や業績が変化していたり、資産構成や負債の状況が変わっているといった事情がある場合には、現在の価値と一致しません。会社が成長しているなら、本来は当時より価値が高くなっていてもおかしくありませんし、反対に業績が悪化していれば、価値が下がっている可能性もあります。
取得価額が分からない場合の基本的な考え方
「昔に取得したので、いくらで買ったか覚えていない」「親から引き継いだので分からない」といったケースもあります。このような場合は、無理に当時の金額を基準にせず、現在の利益・純資産・配当といった情報や類似の会社や過去の取引事例があればその情報を手がかりに、いま時点での妥当なレンジを検討することが重要です。
ここまでが、「適正価格」を考えるうえでの3つの基本的な視点の整理です。
非上場株式の売却でお困りではありませんか?
非上場株式のトラブルならご相談ください
非上場株式の主な評価方法を解説
ここまで見てきた「利益」「純資産」「配当」といった視点は、実際の評価方法としてもさまざまな形で使われています。
株式評価は、状況に応じて複数の方法を組み合わせながら、非上場株式の価値を検討していきます。
ここでは、代表的な株式の評価方法を、できるだけイメージしやすい形で紹介します。
インカムアプローチ(DCF法など)
インカムアプローチは、会社が将来生み出すと見込まれる利益やキャッシュフローに着目する方法です。「この会社はこれからどのくらいお金を生み出すのか」という視点を、そのまま株価の考え方につなげていきます。インカムアプローチには、将来のキャッシュフローを使うDCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)のほか、一定期間の利益をもとに企業価値を割り出す収益還元法なども含まれます。
DCF法の基本的な考え方
DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)は、インカムアプローチの代表的な方法です。
考え方は次のような流れになります。
- 今後数年間にわたって、その会社が生み出すと見込まれるキャッシュフロー(現金収支)を予測する
- 将来手に入るお金は、今のお金よりも価値が低いと考え、「割引率」と呼ばれる率を使って現在の価値に換算する
- その「現在価値」を合計し、会社全体の価値を求める
たとえば、今はあまり利益が出ていなくても、数年後には事業が育って大きな利益を生むと見込まれる会社であれば、DCF法では高い評価が出ることがあります。一方で、将来の見通しが読みにくい会社や、売上や利益が大きく上下する会社では、前提となる予測自体が難しくなることがあります。
DCF法のメリット・注意点
DCF法は、次のようなメリットと注意点があります。
成長性の高い会社や、新しいビジネスモデルを持つ会社の価値を反映しやすく、将来の計画や投資の内容を踏まえて評価できる。一方で、将来の数字の予測に大きく依存するため、前提が変わると評価が大きく動きやすく、少数株主の立場から、必要な情報をすべて入手するのが難しい場合があるという側面もあります。
マーケットアプローチ(類似会社比較法・取引事例法)
マーケットアプローチは、「市場での取引例」を手がかりに評価する方法です。上場会社や、他の株式取引のデータを参考に、「この会社の株式なら、どのくらいの水準が妥当か」を考えます。
類似会社比較法とは
類似会社比較法は、上場している「似た会社」の株価をもとに評価する方法です。
次のような流れになります。
- 業種や規模が似ている上場会社をいくつか選ぶ
- それらの会社の「株価 ÷ 利益」や「株価 ÷ 売上高」といった倍率(マルチプル)を確認する
- 自分の会社の利益や売上に、その倍率を掛け合わせて株価の目安を出す
たとえば、似た会社の株価が「利益の10倍程度」で評価されているなら、自分の会社の利益に「10倍」を掛けて全体の価値の目安を出し、そこから1株あたりの価値を計算していく、というイメージです。
取引事例法とは
取引事例法は、実際に行われた株式の取引価格を参考にする方法です。同じ会社の株式が過去に売買されたときの価格や似た会社の非上場株式の取引例などが手がかりになります。
たとえば、数年前に大株主同士で株式の売買が行われていた場合、そのときの1株あたりの価格や条件を確認することで、今回の取引の参考にすることができます。
ただし、当時と比べて業績や財務状況が大きく変わっている場合には、そのまま当てはめることはできません。
ネットアセット/配当アプローチ(純資産法・配当還元法)
ネットアセットアプローチは「会社が今持っている財産」に着目し、配当アプローチは「株を持っていることで得られる配当」に着目する方法です。
いずれも、これまで説明してきた「純資産の視点」「リターンの視点」に近い考え方です。
純資産法のイメージ
純資産法は、会社の純資産を基準に株価を考える方法です。
- 貸借対照表上の資産と負債から純資産を計算する
- 必要に応じて、不動産などの評価を時価に近づける修正を行う
- 純資産の総額を発行株式数で割り、1株あたりの価値を求める
という流れで検討していきます。
会社が多くの現金や不動産、有価証券などを保有している場合、純資産法で見ると一定の価値が出やすくなります。 一方で、将来の成長性やブランド価値など、目に見えない価値は反映されにくいという面もあります。
配当還元法のイメージと少数株主との関係
配当還元法は、株式を持っていることで得られる配当金を基準に価値を考える方法です。
- これまでの配当実績や、今後見込まれる配当金の額を確認する
- その配当金を、どのくらいの利回りで評価するかを決める
- その結果として、「この配当なら株価はいくらくらいが妥当か」を逆算する
という形でイメージすると分かりやすくなります。
配当還元法は、「株主として受け取る利益」に焦点を当てているため、少数株主の立場との相性が良いとされることがあります。しかし、配当をほとんど出していない会社や、利益を内部に留保している会社の場合、配当還元法だけに頼ると非常に低い価値になってしまうことがあります。
そのため、配当が少ない会社については、配当還元法だけでなく、利益や純資産の情報も含めて総合的に考える必要があります。
税務上の評価(財産評価基本通達)と実際の取引価格の違い
非上場株式について調べていると、「国税庁の財産評価基本通達」「取引相場のない株式の評価」といった言葉を目にすることがあります。これは、主に相続税や贈与税の申告の際に用いるために、国税庁が財産評価基本通達で定めている税務上の評価額のルールです。
この税務上の評価では、非上場株式(取引相場のない株式)について、純資産価額方式、類似業種比準価額方式、これらを組み合わせる併用方式、配当還元方式などの評価方法を用い、会社の純資産、類似上場会社の株価、配当状況などの要素を組み合わせて「相続税・贈与税計算のための評価額」を求める仕組みになっています。
税務評価の方法は株主の区分と会社規模で変わる
財産評価基本通達による評価は、株式を取得した人が同族株主等に当たるかどうか(親族などの近い関係者がまとまって議決権の多くを保有しているか)、発行会社の規模区分はどうか、といった条件によって、計算のルールが変わります。
同族株主等が取得した株式は、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、併用方式といった「原則的評価方式」で評価するのが基本です。これに対して、同族株主等以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、配当還元方式で評価するのが原則とされています。
配当還元方式は、1年分の配当金額を一定の利率(10%)で割り戻し、株式の価額を求める方法です。配当をほとんど出していない会社では、配当還元方式の評価額がかなり低くなることもあるため、「税務評価の数字」だけを前提に売買価格を決めてよいのかは慎重に検討する必要があります。
ここで注意したいのは、税務評価額と、実際の売買の場面で当事者が合意する価格は、必ずしも一致しないという点です。
- 税金の計算では、なるべく画一的な基準が必要になる
- 実際の取引では、会社の事情や交渉の経過、将来の見通しなど、さまざまな要素が価格に影響する
といった違いがあるためです。
少数株主としては、税務評価はあくまで「一つの目安」になり、売買価格そのものは、相手との合意や交渉によって決まるという点を理解しておくことが大切です。
税金の詳しい取り扱いや個別の金額については、必ず税理士などの専門家に相談したうえで判断するようにしてください。
非上場株式の売却でお困りではありませんか?
非上場株式のトラブルならご相談ください
譲渡先別にみる非上場株式の売却と適正価格
非上場株式の「適正価格」を考えるうえでは、会社の利益や純資産といった数字だけでなく、誰に売るかという点も無視できません。譲渡先が変わると、当事者間で重視される評価の考え方が変わるだけでなく、税務上「時価」として問題にされやすいポイントも変わります。
とくに、親族や関係会社など、当事者の距離が近い取引では「著しく低い価額での譲渡」が論点になりやすく、後から税務上の問題が生じることがあります。一方で、第三者との間で条件を詰めて成立した取引では、合意した価格の合理性を説明できる資料が残っているかが重要になります。
ここでは、主な取引類型ごとに、価格の考え方と注意点を整理します。
- 個人から個人:時価と比べて著しく低い価額だと、差額が贈与とみなされるおそれがある
- 個人から法人:著しく低い価額で譲渡すると、売り手側で時価譲渡があったものとみなされる場合がある
- 法人から法人:低額譲渡の場合、受贈益や寄付金など法人課税の論点が出ることがある
- 発行会社による自己株式取得:売却代金の一部がみなし配当として課税される場合がある
非上場株式譲渡 個人から個人(親族・元役員・共同創業者など)
個人から個人への譲渡は、関係者同士の距離が近いことが多く、金額だけでなく人間関係への影響も気になる場面です。代表的なのは、親族同士での持ち株の引き継ぎ、元役員が残った役員や従業員に株式を譲るケース、創業メンバーの一人が抜ける際に、他のメンバーに株式を売るようなケースです。
株式価格の決め方と交渉のポイント
個人同士の取引では、会社の利益や純資産、これまでの配当状況などをおおまかに踏まえながら、1株あたりの目安を話し合って決めることが多くなります。過去に同じ会社の株式が譲渡されたことがあれば、その時の価格が参考材料になりますが、当時と現在とで業績や財務状況が大きく変わっているかどうかも確認する必要があります。
少数株主の立場としては、「言われるままの価格」を受け入れるのではなく、自分なりの根拠や価格レンジを持っておくことが大切です。相手との関係を壊したくない場合でも、なぜその価格なのか一度丁寧に尋ねてみたり、「決算書を見ながら専門家の意見も聞いてみたい」と静かに申し出たりすることで、感情的な対立を避けながら妥当性を検討する余地をつくることができます。
個人間で注意したい税金・名義変更手続き
個人から個人へ株式を譲渡するときは、売却益が出れば税金がかかる可能性があります。
また、時価と比べて著しく低い価額で売ると、時価と対価の差額が贈与により取得したものとみなされ、買い手側で贈与税の問題が生じるおそれがあります。なお、贈与税における「著しく低い価額」の判定は個別の事情で判断され、所得税で用いられる「時価の2分の1」といった基準とは同じではありません。
また、株主名簿を書き換える手続きや、株券発行会社であれば株券の引渡しや回収の扱い方を適切に進めておかないと、後日所有者を巡ってトラブルになることもあります。税金の具体的な扱いや申告方法は税理士に確認しつつ、「価格の話」と「手続きの話」をセットで考えるようにすることが重要です。
非上場株式譲渡 個人から法人(発行会社・オーナー会社など)
次に、個人の株主が会社やオーナー会社(法人)に株式を譲渡するパターンです。発行会社そのものが自社株を買い取る「自己株式取得」のほか、会社と関係の深い別法人に譲渡する場合も含まれます。譲渡先が法人になると、手続きや書類がやや形式的になる一方で、話自体は比較的スムーズに進みやすい側面もあります。
自己株式取得・会社買取の特徴
会社が自社株を買い取る場合には、定款の定めや会社法のルールに沿って手続きを進める必要があります。
具体的には、分配可能額の範囲内で自己株式取得を行わなければならず、取締役会設置会社では取締役会決議、そうでない会社では株主総会の決議が求められる場合もあります。会社の資金状況や金融機関との関係を踏まえて、取得のタイミングや金額が検討されます。
会社側には、少数株主を減らして株主構成を整理したい、将来の株主間トラブルを避けたい、といった意図があることも少なくありません。
また、発行会社による自己株式取得に応じて株式を売却した株主については、売却代金の全額が譲渡所得になるのではなく、その一部が税法上の配当(みなし配当)として課税される場合があります。
どの程度がみなし配当とされ、どの程度が譲渡所得として扱われるかは、会社の資本等の額や株式の取得価額との関係によって変わるため、具体的な税務上の取扱いは税理士に確認することが重要です。
一方で、少数株主にとっては、買い手が会社かその関係法人にほぼ絞られてしまい、「他の候補者と価格を比較する」ということが難しくなりがちです。その結果、提示された条件が唯一の選択肢のように感じられ、交渉をためらってしまうことがあります。
個人から法人へ売るときのメリット・デメリット
個人から法人への譲渡には、話し相手が明確で交渉の窓口もはっきりしているというメリットがあります。将来的にその会社と関わらない前提であれば、株式をまとめて引き取ってもらうことで関係を整理しやすくなる面もあります。
その一方で、「会社以外に売る先が見当たらない」という状況になりやすく、価格が低めに設定されやすいことには注意が必要です。会社の財務状況や業績を細かく知らされていない状態で、「この金額が精一杯です」と言われてしまうと、それ以上の交渉がしにくく感じられるかもしれません。少しでも疑問がある場合は、決算書などを確認し、自分なりに利益や純資産から目安を考えたうえで、弁護士や税理士に一度相談してみる価値があります。
非上場株式譲渡 法人から法人・その他のパターン
少数株主が直接売り手になるケースだけでなく、会社グループ全体の動きとして、法人から法人へ株式が移動することもあります。グループ再編や事業提携の強化、投資ファンドによる株式の売却などが代表的な例です。こうした大口の取引は金額も大きく、契約条件も複雑になりやすいため、専門家が関与しながら慎重に進められることが一般的です。
よく見られる「法人から法人」譲渡のパターン
法人同士の取引では、親会社が子会社の株式の一部を別のグループ会社に移したり、事業パートナーに一部の株式を譲渡して関係を強化したりすることがあります。また、ある法人が保有していた株式を、別の投資会社に売却するようなケースも見られます。いずれの場合も、契約の相手は法人同士ですが、その影響は会社全体に及びます。
少数株主が知っておきたいポイント
こうした法人間の動きは、少数株主にも間接的な影響を及ぼすことがあります。大口株主が入れ替われば、会社の方針や経営陣の顔ぶれが変わる可能性があり、その結果として、少数株主に対して株式の売却を求める提案がなされることもあります。条件によっては、「他の株主にも同じ条件で買い取りを提案する」といった扱いになる場合もあります。
誰に売るかで「適正価格」の考え方はどこまで変わるのか
ここまで見てきたように、個人から個人、個人から会社・オーナー会社、法人から法人など、譲渡先によって話の進み方や交渉のしやすさが変わります。とはいえ、どのパターンであっても、少数株主として意識しておきたい共通の考え方があります。
譲渡先によって変わる点・変わらない点
譲渡先によっては、利益を重視した評価が使われやすい場面もあれば、純資産を基準にした価格が基準になりやすい場面もあります。支払方法や時期、他の条件との組み合わせが重要になることもあれば、「一括でいくら」という単純な形になることもあります。
一方で、どの場合でも共通して大切なのは、自分なりの価格の目安や、「これより明らかに低いなら売らない」というラインを持っておくことです。そのうえで、利益・純資産・配当といった基本的な情報を可能な範囲で確認し、提示された価格と見比べる姿勢が重要になります。
もし、「どう考えても安すぎるのではないか」「自分だけが損をしているのではないか」という不安が少しでもある場合には、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。誰に売るかによって交渉の戦い方は変わりますが、「納得できる根拠を持って決める」という点は、どのパターンにも共通するポイントです。
非上場株式の売却でお困りではありませんか?
非上場株式のトラブルならご相談ください
少数株主が安く買い叩かれないための進め方
ここまで見てきたとおり、非上場株式には「市場価格がない」「情報が少ない」「譲渡制限がある」というハンデがあります。
そのうえで安く買い叩かれないためには、感覚だけで話をするのではなく、入手できる情報から「自分が納得できる幅」を作ったうえで交渉に臨むことが大切です。以下では、少数株主の方が押さえておきたい順番を説明します。
まずは「自分なりの株式の売却価格レンジ」を持つ
相手から提示された金額が高いか安いかを判断するには、こちら側でも「目安」を持っておく必要があります。完璧な評価をする必要はありませんが、「このあたりの幅なら許容できる」という価格レンジを持っておくと、交渉の軸がぶれにくくなります。
評価方法を組み合わせて目安を作る
価格レンジを考える際には、1つの数字だけに頼るのではなく、いくつかの方法をざっくり組み合わせるとイメージしやすくなります。たとえば、会社の利益から「利益の何年分くらいか」という視点で考えてみたり、純資産から1株あたりの価値を計算してみたり、配当が出ている会社であれば、配当金を基準にしたイメージも補助線になります。
DCF法のように将来のキャッシュフローを重視する考え方も、成長が期待できる会社では参考になります。ただ、将来の予測には幅があるため、「この会社の将来性をどう見るか」という自分なりの見方を整理したうえで、他の視点と合わせて検討することが大切です。数字を細かく作り込むよりも、「利益ベースだとこのくらい」「純資産ベースだとこのくらい」と複数の目安を持ち、それらを踏まえて総合的に価格レンジを考えるイメージで十分です。
「これ以下なら売らない」ラインを決める
おおまかな株式の売却価格レンジを考えたら、その中で「ここを下回るなら、いったん売らない」というラインを決めておくと、交渉の途中で気持ちが揺れにくくなります。話し合いの場では、相手のペースや雰囲気に押されてしまい、「本当は納得していないのに承諾してしまう」ということも起こりがちです。
あらかじめ、自分の中で最低限許容できる水準を決めておけば、そのラインを踏まえて「これ以上は下げられない」と冷静に判断しやすくなります。逆に、ラインを決めないまま話を進めると、あとになってから「なぜあの金額で合意してしまったのか」と後悔する原因になりかねません。
情報を揃える:会社の業績・純資産・配当の確認
価格レンジを考えるには、会社の状況に関する基本的な情報が欠かせません。すべてを把握するのは難しくても、「最低限ここだけは見ておきたい」というポイントを押さえることで、自分の感覚と提示された価格とのズレを確認しやすくなります。
入手できる範囲の資料から確認する
まずは、株主として受け取っている資料を見直してみることが出発点になります。株主総会の招集通知に添付されている計算書類や、決算報告の資料が手元にあれば、売上高や利益、純資産の水準、配当の有無や金額などを確認できます。また、会社によっては、株主向けに事業の見通しを説明する資料を配布していることもあり、その内容も参考になります。
これらの資料が全く届いていない場合や、長期間送られてきていない場合には、その状況自体が問題になることもあります。株主には、会社法に基づいて計算書類や会計帳簿、株主名簿などの閲覧や謄写を請求できる権利が認められているため、まずは会社に対して資料の提供や閲覧の機会を求めることが考えられます。
それでも合理的な説明や対応が得られないようであれば、法的な手段も含めて検討するために早めに弁護士に相談する余地があります。
価格の話に入る前に確認しておきたいこと
会社から提示された金額が妥当かどうかは、数字の計算だけでは判断しにくいことがあります。少数株主の方でも、次の項目を押さえるだけで「確認すべき論点」が見えやすくなります。
- 自分の保有株式の種類(普通株式か、種類株式か)と株数
- 持株比率(議決権割合がどの程度か)
- 定款の譲渡制限の内容(承認が必要か、承認機関はどこか)
- 株券発行会社かどうか(株券の有無)
- 直近数期の業績(売上・利益の増減)と純資産の増減
- 配当の有無、配当額の推移(無配かどうかも含む)
- 大きな資産の有無(不動産・有価証券など)と負債の状況
- 過去に同社株式の売買があったか(あれば価格や条件)
これらは、手元の株主向け資料だけでなく、定款や登記事項証明書、会社からの開示資料(計算書類等)から確認できることがあります。
数字を完全に理解できなくても「方向性」を見る
決算書に慣れていないと、細かな数字や専門用語に圧倒されてしまうかもしれませんが、最初から完璧に読みこなす必要はありません。
少なくとも、売上や利益がここ数年で増えているのか減っているのか、純資産は積み上がっているのか減っているのか、配当は出ているのかいないのか、といった「方向性」だけでも把握できれば、価格の妥当性を考える際の大きな手がかりになります。
このように、少数株主が安く買い叩かれないためには、「感覚的に高い・安い」と感じるだけで判断するのではなく、一定の価格レンジを持ち、情報を集め、伝え方や条件の組み立て方を工夫することがポイントになります。
非上場株式の譲渡で最低限おさえたい税金・法務のポイント
非上場株式をいくらで売るかを考えるときは、株式の売却価格だけでなく、税金や法律面での基本的な注意点も意識しておく必要があります。ここでは、細かい条文や計算式には踏み込まず、「ここだけは押さえておきたい」というポイントに絞って整理します。
非上場株式譲渡 個人間 税金の基本イメージ
株式を売って利益が出た場合、多くのケースではその利益に対して所得税と住民税がかかります。非上場株式の売却益は、原則として「株式等に係る譲渡所得等」として他の所得と区分して計算される申告分離課税の対象となります。
具体的な税率や損益通算の可否は税制改正の影響も受けるため、「売却益がまったく非課税」というわけではないことを踏まえつつ、最新の取扱いについては税理士に確認することが大切です。
譲渡益にかかる税金と、低すぎる価格のリスク
個人が非上場株式を売却して利益が出た場合、その利益は原則として株式等に係る譲渡所得等として課税されます。税額は、譲渡益の金額に一定の税率を乗じて計算されますが、他の株式の損失との損益通算や繰越控除の有無などによっても最終的な負担額が変わることがあるため、具体的な金額は税理士に確認する必要があります。
一方で、時価と比べて著しく低い価額で株式を譲渡した場合、「本来もっと高く売れるはずなのに、わざと安く譲ったのではないか」と見なされ、時価と対価との差額の全部または一部が相続税法上のみなし贈与として贈与税の対象になるおそれもあります。たとえば、親族間での取引や、支配株主との関係が近い場合には、そのような評価がされやすくなります。
このため、単に税金を抑える目的だけで不自然な価格を設定するのは危険です。株式の譲渡価格について不安がある場合は、税金の面も含めて、早めに税理士など専門家に相談しておくと安心です。
譲渡制限・会社の承認が必要なケース
非上場会社の株式には、多くの場合「譲渡制限」が付いています。これは、見知らぬ第三者が突然株主になることを防ぐための仕組みですが、少数株主が株式を売ろうとしたときにも大きく影響します。
定款の内容と承認手続きの確認
定款で「株式を譲渡するには会社の承認が必要」とされている場合、株主が自由に譲渡先を選べないことがあります。
この場合でも、売り手と買い手の間では株式譲渡契約を結べますが、会社の承認がないままでは株主名簿を書き換えてもらえず、買い手が会社に対して株主としての権利を行使できない状態になり得ます。価格と同じくらい、「承認」と「名義書換」をどう進めるかが重要です。
そのため、株式の譲渡を検討する際には、まず定款でどのような譲渡制限が定められているかを確認することが重要です。承認の有無や手続きの流れ、会社が承認しない場合にどのような扱いになるかを理解していないと、「せっかく譲渡先を見つけたのに、結局承認されず時間だけが過ぎてしまう」といった事態に陥りかねません。
定款や会社のルールを読んでも分かりにくいと感じる場合には、その段階で弁護士に相談し、取れる選択肢や手続きの進め方を確認しておくと、無駄な動きを減らすことができます。
譲渡承認請求書に書くこと(例)
譲渡承認の手続きでは、会社に対して「譲渡承認請求書」を提出する形になることが多いです。会社ごとに書式は異なりますが、一般的には次のような事項を記載します。
- 譲渡しようとする株式の種類と数
- 譲受人(買い手)の氏名・名称
- 会社が譲渡を承認しない場合に、会社または指定買取人に買い取りを求めるかどうか
「買い取りを求めるかどうか」は、後で会社が不承認にした場合の流れに関わるため、記載の意味を理解したうえで判断することが大切です。
会社から返事がない場合は「承認された扱い」になることがある
譲渡承認請求を出したのに会社から返事が来ないと、「結局どうなるのか」が分からず不安になりがちです。会社法上は、会社が原則2週間以内に承認・不承認の決定を通知しないと、承認された扱いになることがあります(会社法145条)。
ただし、会社の状況や定款、通知の方法によって争いになる場面もあるため、「返事がないから大丈夫」と決めつけず、書面での記録を残しながら進めるのが安全です。
名義書換と株券の引渡しを後回しにしない
譲渡がまとまったあとに多いのが、「代金は受け取ったが名義が変わっていない」「株券の扱いが曖昧なまま終わった」というケースです。
株券発行会社では株券の引渡しが必要になりますし、株券が見当たらないと手続きが止まることもあります。名義書換は会社側の手続きが必要になるため、株式譲渡契約書の中で、名義書換の申請や必要書類の提出、株券の引渡しのタイミングまで決めておくと、後日のもめごとを避けやすくなります。
株式譲渡契約書でありがちな落とし穴
株式の譲渡を行う際には、口頭の約束だけで済ませるのではなく、通常は株式譲渡契約書を作成します。ところが、契約書の内容を十分に理解しないまま署名・押印してしまい、後から想定していなかった義務を負うことになった、という相談も少なくありません。
株式の売却価格以外の条項にも目を通す
契約書には、売買価格や支払方法だけでなく、さまざまな条項が含まれます。売り手の側が会社の状況について一定の説明責任を負う「表明保証条項」や、一定期間同じ業種での事業を行わないことを求める「競業避止条項」、トラブルが起きたときの解決方法を定める条項などが盛り込まれていることもあります。
数字の部分に気を取られていると、こうした条項を見落としがちですが、場合によっては価格以上に重い負担となることもあります。また、「簡単な書面だから大丈夫」と言われて署名したところ、後で内容が不利だったことに気づいた、というケースもあります。契約書を渡されたときには、その場ですぐにサインを求められてもいったん持ち帰り、可能であれば弁護士に内容を確認してもらうことを検討した方が安全です。
トラブルになりやすい場面と回避策
非上場株式の譲渡は、相手が会社やオーナーであることが多く、関係性も長く続いてきたものであるため、「トラブルにはしたくない」と考える方がほとんどです。それでも、条件の認識の違いや支払の問題から、後になって紛争になることがあります。
よくあるトラブルと防ぎ方
たとえば、支払期日になっても代金が支払われない、支払が遅れたままになる、支払の途中で条件の変更を一方的に求められる、といったトラブルがあります。また、「株式は渡したのに株式の名義書き換えがされない」「合意していない価格に一方的に変更された」といった相談も見られます。
こうしたトラブルを防ぐためには、口頭の約束だけに頼らず、価格・支払方法・支払期日・株券や株式の名義書き換えの扱いなどを、できるだけ具体的に書面に残しておくことが重要です。相手が信頼できる相手であっても、「念のためお互いの勘違いを防ぐために書面にしておきましょう」と伝えれば、角を立てずに書類作成の必要性を説明しやすくなります。
それでも不安が残る場合や、すでに約束と異なる対応がされている場合には、早めに弁護士など専門家に相談し、どのような対応が可能か確認しておくと、被害が大きくなる前に手を打つことができます。
よくある質問(非上場株式の譲渡・価格)
Q. 会社やオーナーからの提示価格が適正か分かりません。何を見ればよいですか?
まずは「利益」「純資産」「配当」の3点を見て、提示額がその会社の状態とかけ離れていないかを確かめます。あわせて、過去に同社株式の売買があったか、類似の条件で他の株主にも買い取りの提案が出ているかが分かると、比較材料になります。
Q. 譲渡承認請求を出したのに、会社が返事がありません。放置してよいですか?
会社法上は、請求日から原則2週間以内に通知がないと承認された扱いになることがあります。ただし、通知の有無や到達の争いが起きることもあるため、書面で請求し、送付の記録を残したうえで進める方が安全です。
Q. 株券が見つかりません。株式の譲渡はできないのでしょうか?
株券発行会社の場合、株券の引渡しが前提になるため、株券がないと手続きが止まりやすくなります。この場合でも、会社に対して再発行や代替手続きが必要になることがあり、早めに会社へ確認することが重要です。
Q. 親族に安く譲りたいのですが、贈与税がかかりますか?
個人間で時価より著しく低い価額で譲渡すると、差額が贈与とみなされ、買い手側で贈与税の問題が生じるおそれがあります。「著しく低い価額」に当たるかどうかは個別事情で判断されるため、金額の根拠を作ったうえで税理士に確認することが安心です。
いつ誰に相談すべきか?弁護士に依頼するメリット
非上場株式の譲渡では、税金の問題と法律の問題が絡み合うため、「税理士に相談するべきか、弁護士に相談するべきか分からない」という声も見られます。ここでは、相談先の目安と、弁護士に依頼することで期待できるサポート内容について整理します。
税理士と弁護士の役割分担
まずは、税理士と弁護士の役割を大まかに分けてイメージしておくと、誰に何を相談すればよいかが分かりやすくなります。
税金の計算や申告手続き、節税の可能性など、税務の中身に関する具体的なアドバイスは、税理士の専門分野です。譲渡益に対してどの程度の税負担が生じるか、贈与と評価されるリスクがどのくらいありそうか、といった点は税理士の意見を聞く必要があります。
一方で、相手方との交渉、株式譲渡契約書のチェック、譲渡制限や名義書き換えに関する法的な手続き、トラブルが生じた場合の対応は、弁護士の領域です。価格の妥当性をめぐって対立が生じている場合や、契約書の条項が不利ではないか心配な場合、会社との関係がこじれつつある場合などは、弁護士に相談する意義が大きくなります。
税金と法律の両方が絡む場面では、弁護士が窓口となって税理士と連携しながら進めるという形も考えられます。
少数株主が後悔しないために
非上場株式の譲渡は、「いくらが適正なのか分からない」「相手との関係を悪くしたくない」という不安がつきまといます。その結果、十分に検討しないまま相手の言い値で売ってしまい、あとになって「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。
非上場株式の価格を考えるときには、利益・純資産・配当といった複数の視点がありますし、DCF法など将来のキャッシュフローを重視する方法もあれば、純資産法や配当還元法のように財産や配当に着目する方法もあります。譲渡先が会社なのか、オーナー個人なのか、他の株主なのかによって、交渉の進め方も変わってきます。
大切なのは、完璧な計算を自分ひとりでしようとすることではなく、「なぜその価格なのか」を説明できる根拠をできる範囲で持ち、自分なりの価格レンジと「これ以下なら売らない」というラインを決めておくことです。
そのうえで、疑問や不安がある場合には、早めの段階で税理士や弁護士に相談し、税金と法律の両面から不利にならないように進めることが、後悔しないための近道です。