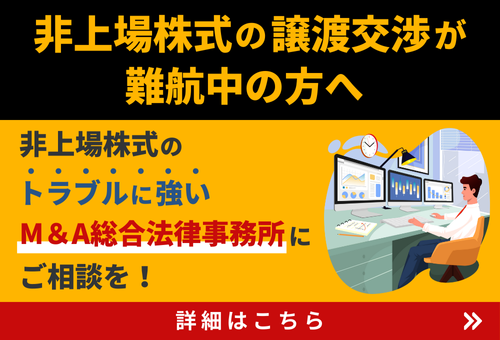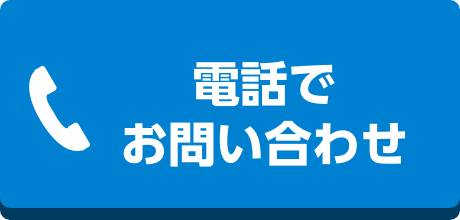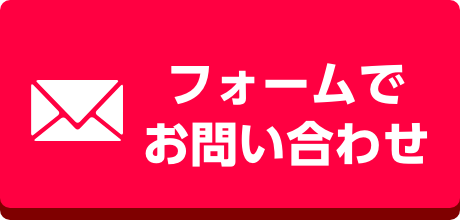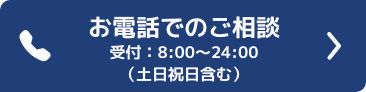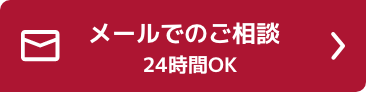非上場株式・少数株式トラブルの解決事例9【創業家が番頭に会社を乗っ取られた事例(創業株主による売却解決事案)】

事案の概要
依頼者は、非上場製造業会社の創業家一族に属する元取締役であり、数パーセントの株式を個人で保有していました。創業家全体としても持株比率は数十パーセント程度に留まっていましたが、経営実務を担っていた番頭(現社長)は徐々に経営権を掌握し、実質的な支配権を確立していました。
長年にわたって創業家一族内での連携が取れず、一部の親族株主は経営に不満を抱きつつも株式を低廉な価格で売却しており、その結果、創業家全体の持株比率は低下を続けていました。依頼者も、経営への影響力が失われた現状において株式を保有し続ける意味が乏しいと判断し、現経営陣に株式の買取を申し入れました。
しかし、会社側は依頼者を他の従業員株主と同列に扱い、「退社時に額面価格で買い取ることが原則である」と主張しました。さらに、一部の株式については所有権自体を否定する姿勢を示しました。創業家の地位を背景に経営を担ってきた依頼者にとって、この対応は到底受け入れ難いものであり、当事務所にご依頼がありました。
紛争・主張論点
- 会社が株式の所有権を一部否定し、株主名簿上の権利確認を争点化した点。
- 会社が額面価格をもって買取価格とすべきと主張した点。
- 依頼者側が時価純資産法および収益還元法の双方を組み合わせ、企業価値を総合的に評価した点。
- 創業家株主間で意思統一が取れず、会社支配権を番頭側が徐々に掌握していった点。
- 訴訟および仮処分の申立てを通じて、株主権確認と同時に買取価格の適正化を図った点。
当事務所の対応の流れ
- 株主権確認および仮処分申立て
当事務所は、会社が株式の一部について所有権を否認していたため、まず株主名簿記載および株主権の確認を求める仮処分を申立てました。これにより、依頼者が適法に株主であることを前提として交渉を進める法的基盤を確立しました。 - 私的鑑定および主張立証の準備
依頼者は公認会計士に依頼し、私的鑑定を実施しました。評価方法としては、会社の保有資産に基づく時価純資産法に加え、営業利益および将来キャッシュフローの割引現在価値を基礎とする収益還元法を併用しました。これにより、会社が主張する「額面評価」に対し、事業継続性を反映した実質価値を示すことができました。 - 会社側の主張と対立構造の顕在化
会社側は、依頼者を「退職従業員と同一視」し、株式は名目的なものであると主張しました。また、会社側は独自に会計士による内部評価書を提出し、額面価格(1株当たり500円程度)をもって買取価格とするとの立場を維持しました。依頼者鑑定との乖離は十数倍に及び、交渉は完全に決裂しました。 - 訴訟および裁判所鑑定の実施
当事務所は、株式買取価格決定を求めて裁判所に申立てを行いました。裁判所は、双方の評価乖離が極めて大きいことを踏まえ、企業価値評価の専門鑑定人を選任しました。当事務所は、会社の実績利益率、固定資産回転率、無形資産の貢献度等に関する資料を提出し、営業利益の安定性を立証しました。 - 裁判所の和解勧告および合意形成
裁判所鑑定では、会社の資産内容を基礎にしつつも、営業利益を反映する収益還元価値を加味した評価額が示されました。この評価額は、会社主張額の約六倍、依頼者鑑定額の約八割程度の水準でした。裁判所からは和解勧告がなされ、当事務所はこれを受けて会社側代理人と和解協議を行い、最終的に時価純資産価格と収益還元価格をおおむね均等に考慮した価格水準で合意が成立しました。 - 買取および履行
最終的に、会社が依頼者保有株式を買い取る内容で和解が成立しました。決済は一括支払とされ、依頼者の保有株式は譲渡制限承認決議を経て名義書換が完了しました。
結果
本件は、長期間にわたり創業家と番頭の間で潜在化していた支配権争いに端を発した事案でしたが、法的手続と経済的交渉を併行して進めたことにより、円滑に解決することができました。会社側が当初主張していた額面評価に比して、和解による買取価格は数倍の水準となりました。依頼者は株式を適正価格で売却し、創業家としての立場を整理できたことで、長年の経営上のしがらみを解消する結果となりました。