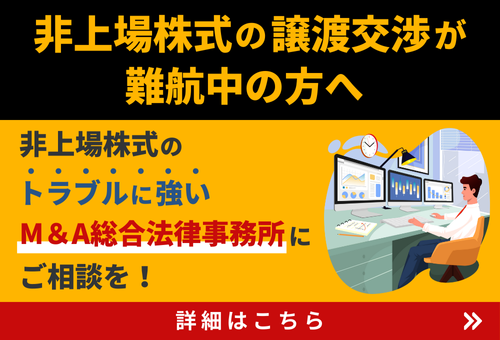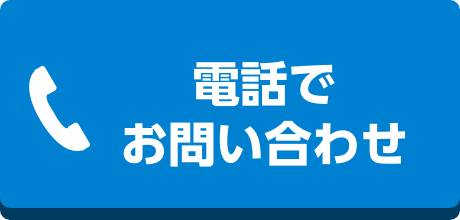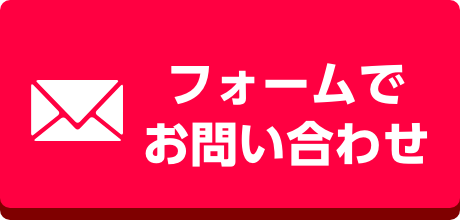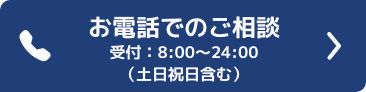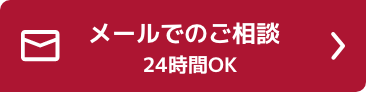株式譲渡承認拒否に伴う株券の供託とは?手続きの流れ・株券がない場合の対処法・注意点を詳細解説
お困りではありませんか?

近年、株式譲渡がよく行われます。譲渡される株式が非上場株式の場合には、株式譲渡の承認が拒否されてしまい、会社などに株式を買い取ってもらうこともあるでしょう。
もっとも、非上場株式を取り扱う会社の中には株券を発行する会社もあり、そのような会社の場合には、「株券の供託」という手続きをすることもあります。
そこで、この記事では、非上場株式における株式譲渡の承認拒否に伴う株券の供託について、詳しく説明していきます。
株式譲渡承認拒否に伴う株券の供託という制度について
会社法には、非上場株式の譲渡承認の拒否に伴う株券の供託という制度が存在します。
これは、非上場株式の譲渡承認を拒否されて、株券発行会社または指定買取人に株式を買い取ってもらう場合に、株券発行会社から交付される株券を供託所に供託するという制度です。
株券発行会社の場合、株券の供託をすることで株式の買い取り手続きが完了します。しかし、株券の供託をしなければ、株式の買い取りを解消されてしまいます。
以下では、株式譲渡の承認が拒否された場合に伴う株券の供託について、手続きの流れや株券がない場合の対処法、その際の注意点などを解説します。
会社の承認を要する株式譲渡とは
株式譲渡は、通常は売主と買主との間で自由に行うことができます。
もっとも、譲渡制限株式を譲渡する場合に、会社に対して株式の取得を主張するためには、会社による株式譲渡の承認が必要となります。これは、会社経営に悪影響を及ぼす者が株主になることを防止するためです。
| *譲渡制限株式とは、株式を譲渡するときに会社による承認を要する旨の制限が付いている株式のことを言います。 |
そして、株式譲渡の承認決議は、原則として株主総会による特別決議、また取締役会設置会社の場合には取締役会による決議を経る必要があります。
しかし、譲渡制限株式を発行する会社には、親族経営などの理由により、新たな株主を受け入れないような会社もあります。そのため、株式譲渡の承認が拒否される場合も多いです。
その場合、会社または会社が指定した者(指定買取人)に株式を買い取ってもらうことになります。その際に、株券の供託という手続きが必要となることがあります。
株券及び株券発行会社とは
株式会社の中には、株券を発行する会社も存在します。
ここで、株券とは、株式について株主の地位や権利を表章するための有価証券のことを言います。
株券を発行する旨を定款で定めた会社のことを株券発行会社と言います。
株券発行会社は、株式を発行した日以後に、その株式にかかる株券を発行します。
株式譲渡承認拒否に伴う株券の供託とは?
株式譲渡承認請求から株券の供託までの手続き
株式譲渡により株式を譲り受けた人(以下、「株式取得者」と言います)は、以下のような流れで株式譲渡承認請求をして、株券の供託まで行うことになります。
-
株式取得者から会社に対して、株式譲渡の承認を請求する(会社法137条1項)
-
会社は、株式譲渡を承認するか否かについて、株主総会または取締役会で決定する(139条1項)
-
会社から株式取得者に対して、株式譲渡の不承認決定を通知する(139条2項)
-
会社は、株主総会において、会社or指定買取人による株式の買取りを決定する(140条)
-
会社が株式を買い取る場合(141条)
- 会社から株式取得者に対して、会社が株式を買い取る旨を通知する
- 会社は供託所に供託し、供託を証する書面を株式取得者に交付する
- 株式取得者は、2の書面の交付を受けてから1週間以内に、株券を供託所に供託する
- 株式取得者から会社に対して、株券を供託した旨を通知する
-
指定買取人が株券を買い取る場合(142条)
- 指定買取人から株式取得者に対して、指定買取人が株式を買い取る旨を通知する
- 指定買取人は供託所に供託し、供託を証する書面を株式取得者に交付する
- 株式取得者は、2の書面の交付を受けてから1週間以内に、株券を供託所に供託する
- 株式取得者から指定買取人に対して、株券を供託した旨を通知する
以上が手続きの流れになります。なお、これはあくまで株券発行会社である場合の手続きとなります。
会社が株式を買い取る場合について
会社が株式を買い取る場合については、会社法141条3項に規定があります。
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。(141条3項)
|
*譲渡等承認請求者とは、株式の譲受人である株式取得者のことです。 |
株式取得者が会社から、会社が株式を買い取る旨の通知を受け、さらに、株式譲渡代金の供託を証する書面の交付を受けた場合には、交付を受けた日から「1週間以内」に、株券を供託所に供託し、その旨を会社に通知しなければなりません。
|
*供託とは、金銭や有価証券などを供託所または一定の者に預けて、その管理を委ねる制度を言います。 *供託所とは、法務局・地方法務局またはそれらの支局のことを指します。供託所の場所については、法務省または法務局のホームページに記載してあります。 |
指定買取人が株式を買い取る場合について
指定買取人が株式を買い取る場合についても同様の規定があります。
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。(142条3項)
株式取得者が指定買取人から、指定買取人が株式を買い取る旨の通知を受け、株式譲渡代金の供託を証する書面の交付を受けた場合には、交付を受けた日から「1週間以内」に、株券を供託所に供託し、その旨を指定買取人に通知しなければなりません。
期限内に供託しなかった場合について
株式取得者が、会社または指定買取人から供託を証する書面の交付を受けた日から「1週間以内」に、株券を供託することができなかった場合には、会社又は指定買取人は、株式取得者との間の株式の売買を解消することができます。
参考:会社法141条4項、142項4項
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。(141条4項)
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。(142項4項)
したがって、株券の供託の手続きは、予め、よく準備しておく必要があります。
株券がない場合の手続について
株券が発行されていない場合の手続
昨今では、株券発行会社においても、株券を発行していないところもあります。公開会社でない株券発行会社の場合、株主からの請求がない限り、株券を発行しないことができるためです(会社法215条4項)。
|
*公開会社と公開会社でない会社(非公開会社)について 公開会社:譲渡承認を要しない株式を発行する株式会社のこと 非公開会社:譲渡承認の制限付きの株式を発行する株式会社のこと |
そのような場合に株券を供託するように言われても困ってしまうと思います。しかし、法律に株券の供託が求められている以上、株券の供託を行わなかった場合は、株式の売買を解消されてしまいます。
そこで、会社が株券発行会社であるかどうかを調べる必要があります。これは、商業登記簿を取り寄せて確認することができます。
そして、株券発行会社であるのに株券を発行していない場合は、株券の新規発行を請求する必要があります。
株券不所持の場合の手続
また、株券発行会社で株券を発行しているものの、会社にて保管する運用(株券不所持)となっている場合もあります。この場合には、自己の株券が存在するはずなので、株券の再交付をしてもらう必要があります。
ただ、会社と株主がトラブルになっている場合など、会社が嫌がらせで株券の新規発行や株券の再交付を拒否したり引き延ばすこともままありますので、その可能性も踏まえて、株式譲渡承認請求をどのようなスケジュールで進めていくかを事前に考えておかなければいけません。
会社が株券発行を拒否する場合の対処法とは
会社が株券発行を拒否する場合とは
会社としては、譲渡制限株式を取得した株主が株式譲渡承認請求を行っても、株券を供託できなければ、株式買取請求や株価決定申立(株価決定裁判)を行うことができないことは分かっています。
そうすると、会社が株券の発行を拒否して、事実上、譲渡制限株式を取得した株主が、株式譲渡承認請求を行うことや、株式買取請求や株価決定申立(株価決定裁判)を行うことを、阻止する場合もあります。
株券発行拒否への対処法について
上記のような場合、譲渡制限株式を取得した株主は、会社に対して訴訟を提起して、株券を取得する必要が生じてきます。
株券を取得するための訴訟としては、株券の発行請求及び株券の引渡し請求をする裁判(株券発行及び引渡し請求訴訟)が考えられます。
株券発行及び引渡し請求訴訟に勝訴するためには、まず、株主であることを立証する必要があります。
これについては、会社に株主名簿や確定申告書(別表二 「同族会社の判定に関する明細書」)を提出させることができれば、自らが株主であることを立証することができます。
そして、最高裁判例にて、「株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使する場合、株券発行会社に対し、株券の交付を直接自己に対してすることを求めることができる」(最二小判令和6年4月19日)とされているため、要件を満たせば、同訴訟の勝訴判決を得ることは可能だと考えられます。
株券を回収する方法①直接強制
訴訟に勝訴した場合は、強制執行により株券を回収することができます。株券は、その品質が特定されていない債権であり、同種・同量・同等の株券を引き渡すように要求すれば足りるため、強制執行は難しいことではありません。
そして、強制執行を行うのであれば、直接強制による方法が望ましいです。直接強制による強制執行を申し立てた場合、株主は執行官を伴って会社を訪問し、会社を捜索し、株券を発見し、強制的にその占有を取得することができます。これにより、速やかに株券を入手して、次のステップに進むことができるのです。
株券を回収する方法②間接強制
直接強制をするためには、会社が株券を発行していないといけないですが、会社が株券を発行していない場合も多いです。
そこで、会社が株券を発行していない場合は、会社に対して、間接強制による強制執行を行うことになります。
つまり、間接強制による強制執行を申し立てると、執行裁判所が会社に対し、一定の期間を設けて、その期間内に株券を作成して引き渡さない場合には罰金を科すことになります。これにより、会社に株券の発行及び引渡しを間接的に強制するのです。
ただ、間接強制を行う場合は、会社に対して審尋の機会を与える必要があり、裁判手続きを行わなければなりません。
株券発行及び引渡し請求訴訟の注意点
株券発行及び引渡し請求訴訟は、特段の争点が存在しない場合であっても、半年程度の時間がかかります。加えて、強制執行の手続きについても、直接強制によると執行官のスケジュールの確保に日数が必要となり、間接強制による場合でも会社に対する審尋などで一定の期間を要します。
また、直接強制を行っても、想定の場所に株券が保管されていなかったような場合には、強制執行が「空振り」に終わることとなり、やむをえず、間接強制に移行する必要があります。
なお、この間接強制における罰金ですが、会社に対して株券の発行・株券の引渡を強制することができる程度の金額が設定されることとなりますので、ある程度高額な金額が設定されます。そのため、その罰金をもらい続けることでもそれなりの満足を得られるかもしれません。
専門家である弁護士への相談も必要
上述のように、株券の供託の手続は、株券を持っていない場合には、会社に対して株券を発行してもらうことが必要になります。
しかし、会社が株式譲渡の承認を拒否しているのであれば、それは株式取得者を株主と認めたくないとの意思表示のようなものであり、株券の発行をも拒否する可能性があると言えます。
そこで、株券の発行をしてもらうためにも、企業法務に関する専門家である弁護士に相談するのが望ましいです。
また、譲渡制限付き株式を譲り受けると、その後、株券の供託の手続を行う可能性があるので、早めに弁護士に相談しておくなどの対策をとるのがよいでしょう。
スムーズに株式譲渡を行うために
この記事では、株式譲渡の承認を拒否された場合における株券の供託について解説しました。
「株券」や「供託」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、難しい手続きではありませんので、ご安心ください。
譲渡制限付きの株式を取得した時点で、将来どんな手続きがあるのかを確認し、スムーズに株式を買い取ってもらえるように、また、株券を発行してもらえるように対策をとるとよいでしょう。
その際、企業法務の専門家である弁護士に相談することも検討してみてください。
参考:会社法
| (株式会社による買取りの通知) 第百四十一条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。 2 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。 3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。 4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。 |
| (指定買取人による買取りの通知) 第百四十二条 指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 指定買取人として指定を受けた旨 二 指定買取人が買い取る対象株式の数 (種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 2 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。 3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。 4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。 |
お困りではありませんか?