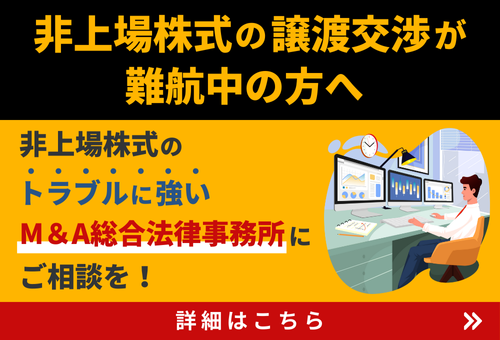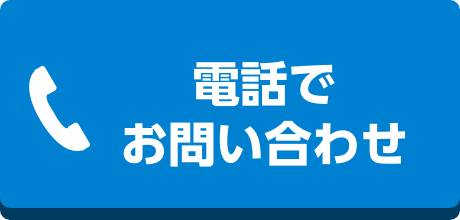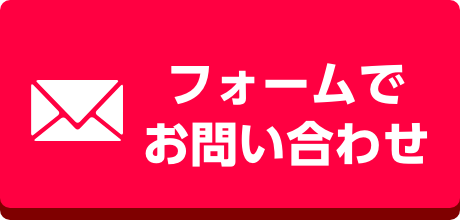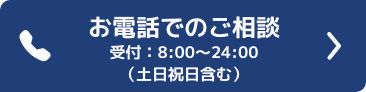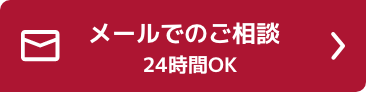非上場株式・少数株式トラブルの解決事例19【少数株主による株式売却請求事例(譲渡制限条項を理由に買取を拒否された事案)】
非上場株式・少数株式の売却で
お困りではありませんか?
お困りではありませんか?

事案の概要
依頼者は、長年勤務していた地方の非上場サービス業会社の取締役を退任後も、約八パーセントの株式を引き続き保有していました。その後、会社は新規事業進出を決定し、実行しました。依頼者が新規事業進出に反対したことで会長との関係も悪化し、依頼者は窓際に追いやられるようになりました。
依頼者は、会社を退職することとし、会社に対し株式の買取を申し入れましたが、会社は「事株式買取義務はない」として拒否しました。さらに会社は、譲渡制限付株式であることを理由に「会社の承認がなければ譲渡できない」と主張しました。会社から提示された株式買取額は、純資産法や収益還元法を曲解した極めて低額な金額であり、依頼者側の株式評価額との差が大きく、当事者間で合意に至りませんでした。
紛争・主張論点
- 会社が株式譲渡制限を盾に株式譲渡を実質的に拒否している点の法的妥当性。
- 会社が純資産法と収益還元に基づき低額評価を提示したのに対し、依頼者が純資産法・収益還元法・DCF法により高額な企業価値を主張した点。
- 当事者双方が公認会計士に依頼して私的鑑定を実施し、株式評価書を提出したが、算定結果に著しい乖離があり合意できなかった点。
- 折り合いがつかず、裁判所における株式買取価格決定手続に移行した点。
- 裁判所における主張立証の結果を基礎に、最終的に社長個人が自己資金により依頼者株式を一括で買い取る形で和解が成立した点。
当事務所の対応の流れ
- 譲渡制限の有効性の検討および株式買取請求の実行
当事務所は、会社法第139条(譲渡制限株式の株式譲渡承認請求)および第144条(会社による株式買取請求)を踏まえ、会社に対し正式な株式譲渡承認請求を行いました。会社側は、第三者に株式を取得されることを恐れ、承認を拒否しましたが、会社による株式買取の意思を示しました。 - 双方による私的鑑定の実施と主張立証
依頼者は会計士に依頼して純資産法・収益還元法・DCF法に基づく私的鑑定を実施しました。株式評価では、会社の純資産に加え営業利益・キャッシュフローの推移から将来の割引現在価値を算出し、主要取引関係や譲渡後の残存資産の収益性も加味しました。
一方、会社側も別の会計士による私的鑑定を提出し、純資産法・収益還元法を基礎とした株式評価額を主張しました。
しかし、両者の株式評価額には、同じような株価算定方式を採用したにもかかわらず、約十倍の開きが生じ、交渉は決裂しました。 - 裁判所手続への移行と公的鑑定の実施
当事務所は、株式買取価格決定申立てを裁判所に提出しました。裁判所では、双方が会社の経営や株式価値について主張立証を尽くし、財務資料・過去の事業譲渡契約書・将来事業計画等を詳細に検討しました。当事務所は、会社側の株価評価の中の継続的収益及び計算過程に虚偽が存在することを示し、裁判所における主張立証で圧倒しました。 - 裁判所鑑定および和解交渉
依頼者側鑑定は、会社の時価純資産価額に加え、残存事業の継続的収益を考慮して、収益還元法ベースでの評価額を提示しました。鑑定結果は会社提示額の約四倍でした。裁判所の和解勧告を受けて、当事務所は会社側代理人と和解協議を開始し、会社資金による株式買取ではなく、代表取締役個人が自己資金で株式買取を行う方向に調整しました。 - 最終合意と履行
最終的に、社長個人が依頼者保有株式を依頼者鑑定額よりやや低い水準で一括買取することで和解が成立しました。株式売買代金は全額一括支払とされました。税務処理および譲渡所得の申告についても当事務所が税理士と連携し対応しました。
結果
依頼者は、株式価値が不透明となっていた非上場株式を、公正かつ実務的な方法で売却することができました。会社側が当初主張していた純資産法による株式評価額の数倍に相当する株式価格での一括売却が実現し、依頼者は長年抱えていた株主関係を整理できました。また、社長個人による株式買取としたことで、依頼者の課税負担への影響を軽減しつつ、実質的な少数株主問題の解消に至った事案です。
非上場株式・少数株式の売却で
お困りではありませんか?
お困りではありませんか?