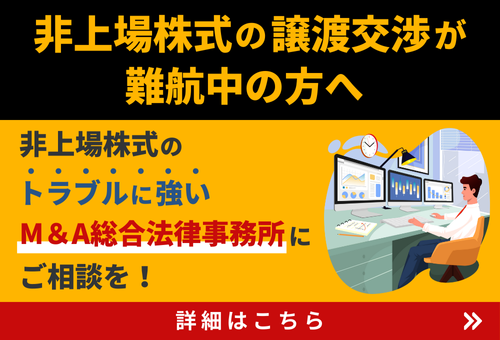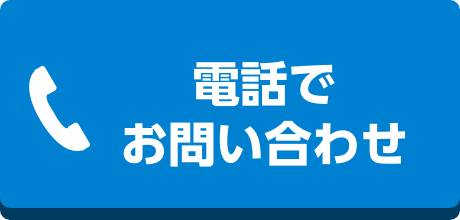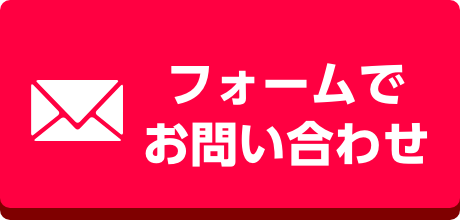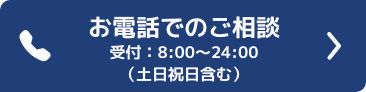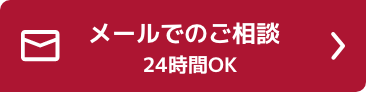非上場株式・少数株式トラブルの解決事例18【退任後株式の買取拒否を乗り越え売却した事例(第三者も含めた売却交渉をした結果売却完了)】
非上場株式・少数株式の売却で
お困りではありませんか?
お困りではありませんか?

事案の概要
相談者は、かつて親族が経営する非上場会社の取締役を務めていましたが、経営方針の相違により退任しました。その後も約十パーセントの株式を保有していましたが、株主総会も開催されず、配当金も支給されず、社長やその親族による公私混同が続き、会社財産は毀損される状態が続いていました。
相談者は株式を売却して関係を整理する意向を示しましたが、会社側は「少数株主である以上、配当還元価格での評価が妥当である」と主張し、非常に低額な株式買取価格を提示しました。これは、会社が利益のごく一部しか配当していない点を前提にしたものであり、実際の事業収益力や無形資産価値は一切考慮されていませんでした。相談者はこの提示に強い不信感を抱き、当事務所に依頼しました。
論点および争点
- 少数株主を理由として配当還元価格での評価を主張することの妥当性
- 配当政策が恣意的である場合における株式価値算定の再検討可能性
- 将来収益力(営業利益・キャッシュフロー)を考慮した評価の導入
- 支配株主が会社ではなく個人として株式買取義務を負う構造の採用
- 合意形成に向けた支払条件および株式買取価格水準の調整
当事務所の対応の流れ
- 会社への株式買取請求と法的主張
当事務所は、会社側に対し正式な株式買取請求を行い、配当還元法の適用が不当であることを明確に主張しました。非上場会社の株価算定において、配当政策は恣意的に設定可能であり、支配株主が配当を抑制している場合には、配当還元価格が実態を反映しない旨を法的根拠をもって指摘しました。 - 株式評価書の提示
依頼者側で収益還元法およびDCF法による株式評価書を作成し、営業キャッシュフロー、WACC、事業計画をもとに合理的な評価レンジを提示しました。株式評価資料には、会社の実際の事業利益率および将来の成長可能性を反映させ、説得力のある数値を提示しました。 - 交渉と合意形成
当初会社側は分割支払を提案しましたが、当事務所は早期解決および金銭的確実性を重視し、一括支払を条件とする合意を求めました。担保設定は行わず、契約履行を信頼ベースで行う方向で交渉を進めました。交渉の過程で、会社代表者個人(社長)が自らの資金で株式を買い取る提案を行い、これを受け入れました。 - 株式売買契約と決済
最終的に、社長個人が相談者の保有株式を一括支払で買い取る内容の合意が成立しました。株式売買価格は当初提示額の約二倍に達し、会社法上・税務上の整理も併せて行われました。
結果
相談者は、長期間流動性のなかった株式を公正な価格で売却し、経営関係を円満に終了させることができました。支配株主である社長個人が直接株式を買い取ることで、株主の課税負担を軽減しつつ、少数株主関係を法的にも実務的にも整理できた事例です。
非上場株式・少数株式の売却で
お困りではありませんか?
お困りではありませんか?