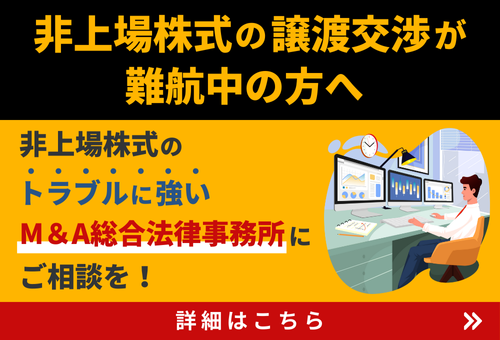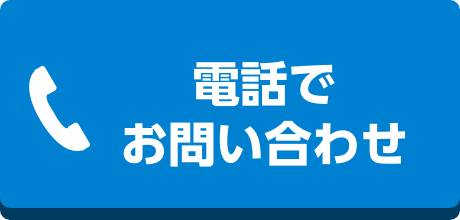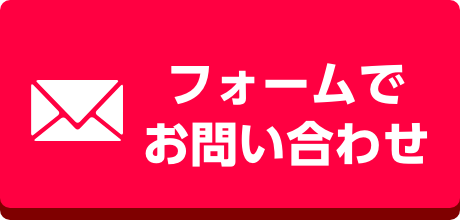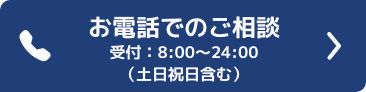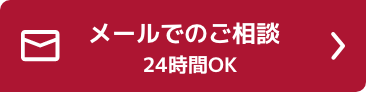非上場株式・少数株式トラブルの解決事例14【実家を離れた次女が同族会社から排斥された事例(遠隔地株主の株式買取交渉事案)】
非上場株式・少数株式の売却で
お困りではありませんか?
お困りではありませんか?

事案の概要
依頼者は、地方の老舗同族会社の創業者の次女であり、創業家の中では筆頭株主でした。結婚後、他県に居住しており、会社の経営には二十年以上関与していませんでした。長年にわたり経営を担ってきたのは、創業者の長男(現社長)およびその子息らであり、依頼者は経営方針の決定や会社の状況について一切の情報提供を受けていませんでした。
依頼者は株主として会社の経営に一定の関心を持ち続けていましたが、配当は全く支払われず、株主総会の開催通知も形式的なものにとどまっていました。依頼者が会社に対して株式の買取を申し入れたところ、会社側は「当社は債務超過状態にあり、株式の価値は0円である」と主張し、買取を拒否しました。さらに、依頼者が決算書類の開示を求めた際にも、会社側は「社外株主への情報提供義務はない」として開示を拒否しました。
しかし、依頼者は会社の製品が地域で高い評価を受け、販売も堅調に推移していることを把握しており、会社の主張する「債務超過」は不自然であると感じ、当事務所に相談されました。
紛争・主張論点
- 会社が債務超過を理由に株式価値を0円と主張する妥当性の有無。
- 配当の長期停止および会計書類非開示が株主権の侵害にあたるか。
- 会計帳簿閲覧謄写請求(会社法第433条)による情報取得の可能性。
- 株式評価手法として、時価純資産法・収益還元法・DCF法のいずれを採用すべきか。
- 訴訟手続を経ずに会社との交渉を通じて合理的な価格での買取を実現する方策。
当事務所の対応の流れ
- 会社財務情報の分析と情報開示請求準備
当事務所は、依頼者から提供された過去の株主総会資料、取引先情報、地域業界紙の記事などをもとに、会社の実態を推測しました。その結果、会社は表面上の負債を大きく計上している一方で、営業利益は黒字を維持しており、実質的な債務超過ではない可能性が高いと判断しました。
会社に対しては、会計帳簿閲覧謄写請求を正式に送付し、開示拒否の場合には訴訟手続を取る旨を明示しました。
- 私的鑑定の実施と交渉戦略の構築
依頼者は公認会計士に依頼し、収益還元法およびDCF法を併用した私的鑑定を実施しました。評価書では、会社の営業利益推移・顧客基盤の安定性・ブランド価値を反映し、会社が主張する「0円評価」を明確に否定しました。当事務所はこの鑑定書を根拠に、会社に対して再交渉を申し入れました。 - 会社側の反論と当事務所の対応
会社側は、「依頼者は経営に関与しておらず、株主としての実質的貢献もない」と主張しました。これに対し当事務所は、株主の持分は経営関与の有無ではなく会社の財務的成果に応じて評価されるべきであることを法的根拠に基づいて説明し、会社の主張が不当であることを明確にしました。 - 交渉の進展と最終合意
当事務所は、会社側が公表を避けたい決算情報を訴訟で開示されるリスクを指摘し、粘り強く交渉を継続しました。会社側は最終的に姿勢を軟化させ、第三者鑑定水準を参考に、依頼者の希望額に近い水準での株式買取を提案。正式な譲渡契約書を締結し、決済が行われました。 - 譲渡および税務処理支援
株式の譲渡承認決議が完了し、名義書換および譲渡代金の支払が実施されました。当事務所は税理士と連携し、譲渡所得の税務申告もサポートしました。
結果
会社が当初主張していた「株式価値0円」という立場は実質的に撤回され、最終的に依頼者の希望額に近い価格で全株式を会社が買い取る形で合意が成立しました。裁判所手続を経ることなく、法的根拠に基づく交渉のみで合理的な解決が実現した事案です。
依頼者は、長年排除されてきた株主としての地位を整理し、経済的利益を確定させることができました。また、会社側も、訴訟化による経営情報の開示リスクを回避することができ、実務上円滑な終結となりました。
非上場株式・少数株式の売却で
お困りではありませんか?
お困りではありませんか?