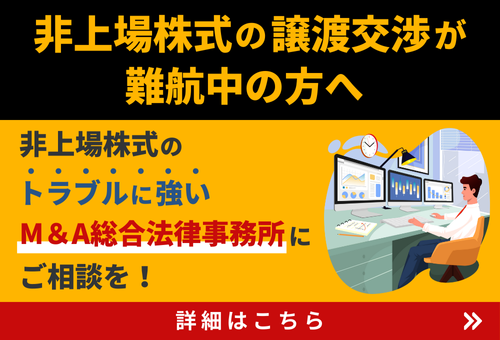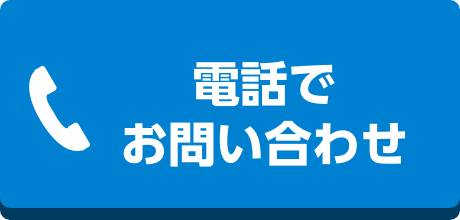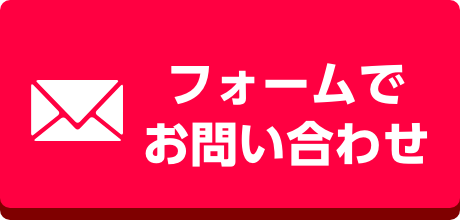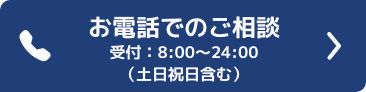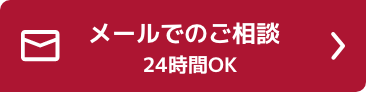非上場株式・少数株式トラブルの解決事例13【オーナーが後継者候補の甥を追い出した事例(後継者排除に伴う退職慰労金請求と株式売却事案)】

事案の概要
依頼者は、地方の老舗非上場会社における創業社長の甥であり、後継者不在であった創業社長から、将来的な後継者候補として取締役に任命されました。依頼者は入社後、経営管理・営業拡大の両面で成果を挙げ、社内外からも次期経営者として期待されていました。
しかし、依頼者の改革志向や独立した経営判断が、創業社長の伝統的な経営スタイルと対立するようになり、両者の関係は次第に悪化しました。創業社長は「甥が自己主張を強め、会社を乗っ取ろうとしている」と周囲に述べ、突如として取締役を解任。依頼者に対して退職慰労金の支払も行わず、さらに依頼者が保有していた株式(発行済株式の約5%)の買取も拒否しました。
依頼者は経済的に困窮し、生活費にも事欠く状態となったため、退職慰労金の支払および株式買取を求める訴訟を提起しましたが、創業社長は「甥である以上、恩義を返すべきであり、金銭請求は道義に反する」と主張し、法的義務を全面的に否定。事案は感情的対立を伴う長期紛争へと発展しました。
紛争・主張論点
- 創業社長による後継者候補解任の正当性および退職慰労金支払義務の有無。
- 株式の譲渡制限規定に基づく会社の買取義務の存否。
- 創業社長が提示した株式評価(額面基準)が実質的に時価を反映していない点。
- 依頼者による会社への経営貢献度および創業社長による一方的排除の不当性。
- 裁判手続における慰労金請求と株式売却を並行して処理する法的・経済的整理。
当事務所の対応の流れ
- 法的構成の整理および請求方針の確立
当事務所は、まず退職慰労金規程および同社の支給実績を精査し、依頼者に対する不支給が株主平等原則(会社法第109条)および役員待遇の公平原則に反することを確認しました。
また、株式譲渡制限規定(会社法第139条以下)のもとでも、会社が譲渡承認を拒否する場合には買取義務を負う(会社法第144条)ことを整理し、二つの請求を並行的に主張する戦略を採用しました。 - 訴訟提起と主張立証活動
依頼者代理人として、退職慰労金支払請求訴訟を提起し、同時に株式買取交渉を進めました。訴訟においては、依頼者の在任中の経営成果(売上拡大率、主要取引先の獲得実績、利益率改善)を証拠として提出し、単なる親族的地位による解任ではなく、経営上の功績をもとに慰労金支払義務があることを主張しました。 - 会社側の反論および当事務所の対応
会社側は、「親族間の内部的信頼関係の破綻に起因する退任であり、退職慰労金は任意支給に過ぎない」と主張しました。これに対し当事務所は、会社が他の役員には一律に慰労金を支給している事実を立証し、依頼者に対する不支給が差別的取扱いであることを明らかにしました。 - 株式評価および第三者売却方針の検討
依頼者が保有する株式については、会社が買取を拒否したため、当事務所は独自に第三者譲渡の可能性を検討しました。公認会計士による私的鑑定を実施し、収益還元法およびDCF法を基礎とした評価書を作成。裁判所に対しても、依頼者が当該株式を適正価格で処分する合理的意図を有していることを主張しました。 - 裁判所判断および解決
訴訟審理の結果、裁判所は、依頼者の経営貢献を認め、退職慰労金全額の支払を命じる判断を示しました。これを契機として、依頼者は株式についても第三者への売却交渉を進め、裁判所の承認のもとで譲渡が実現しました。
結果
最終的に、依頼者は裁判所の判決に基づき、退職慰労金の全額を受領し、保有株式を第三者に適正価格で売却することができました。会社および創業社長による買取拒否という閉鎖的環境の中で、法的手段を用いて現実的な資金回収と地位整理を実現した事案です。
依頼者は、親族経営の枠組みから離脱することで経済的独立を回復し、会社側も訴訟長期化を回避する形で紛争を終結できました。本件は、親族関係を背景とする経営権排除事案において、裁判所が役員慰労金請求と株式売却を制度的に分離しながら、実質的な衡平を図った例として評価できます。