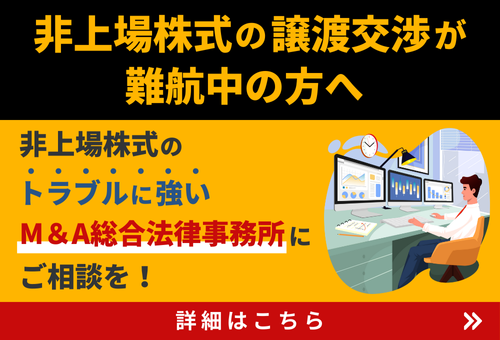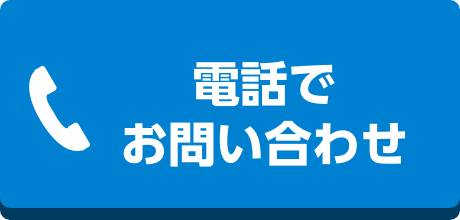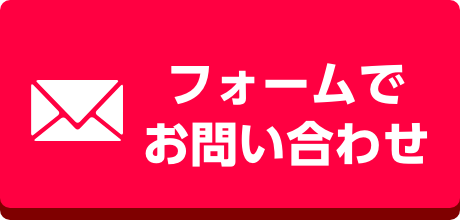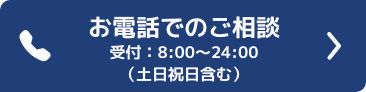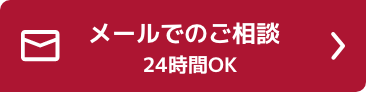非上場株式・少数株式トラブルの解決事例12【オーナーが雇われ社長のことを私情で追い出した事例(退職慰労金請求と株式売却の併合解決事案)】

事案の概要
依頼者は、オーナー創業者が経営する非上場会社において、後継者不在を理由に外部から招聘された代表取締役社長でした。依頼者は就任後、経営改善および組織再編を推進し、業績を大幅に向上させました。しかし、依頼者の実務能力と独立した経営判断が、創業者の意向と対立するようになりました。創業者は、依頼者が自己の方針に従わないことに強い不満を抱き、突如として代表取締役を解任しました。
解任に際し、会社は依頼者に対して役員退職慰労金を一切支払わず、依頼者が保有していた株式(発行済株式の約5%)についても、会社の提示する極端に低い価格での買取を強要しました。提示価格は、額面に近いものであり、依頼者が就任後に築いた企業価値を反映していませんでした。依頼者は、オーナーの私情による一方的な解任と財産権侵害に強い不満を抱き、当事務所に依頼しました。
紛争・主張論点
- オーナー創業者による代表取締役の解任に正当理由が存在しない点。
- 役員退職慰労金支払拒否の不当性。
- 会社が提示する株式買取価格が額面水準であり、適正な時価評価を欠いていた点。
- オーナーの私的感情に基づく経営判断が会社法第355条(善管注意義務)および第330条(忠実義務)に反する点。
- 株式買取交渉と退職慰労金請求を併合的に進める戦略の採用。
当事務所の対応の流れ
- 解任の経緯および退職慰労金請求の法的整理
当事務所はまず、取締役会議事録、株主総会決議書、雇用契約書等を精査し、依頼者の解任が手続的にも実体的にも合理性を欠くことを確認しました。依頼者の解任理由として提示された「方針の不一致」は抽象的であり、会社業績の改善という客観的実績を踏まえれば正当理由を欠くと判断されました。
また、退職慰労金規程および過去の役員支給実績を調査した結果、依頼者に対してのみ支給を拒否することは株主平等原則(会社法第109条)に反することを明らかにしました。
- 株式買取請求と評価方法の確立
依頼者が保有する株式について、当事務所は公認会計士に私的鑑定を依頼し、収益還元法およびDCF法による企業価値評価を実施しました。評価書では、依頼者就任後の収益性改善、キャッシュフロー増加、ブランド価値向上を反映し、会社が提示した額面評価(1株あたり数百円)を大幅に上回る水準を提示しました。
当方評価書を会社に提示し、合理的な時価評価に基づく買取を求めましたが、会社側はこれを拒否し、解任および買取拒否を「経営判断の自由」に基づくものと主張しました。
- 訴訟提起と交渉戦略
当事務所は、退職慰労金支払請求訴訟を提起し、訴訟の過程で株式買取の交渉も併行して進めました。訴訟においては、依頼者が経営改善に寄与した具体的実績(利益率の上昇、コスト削減、取引先拡大等)を立証し、退職慰労金支払義務を主張しました。さらに、オーナー創業者が会社資金を私的支出に使用していた事実も指摘し、経営判断の恣意性を立証しました。 - 裁判所の和解勧告と合意形成
審理の過程で裁判所から和解勧告があり、裁判所は、退職慰労金の全額支払に加え、依頼者が保有する株式の公正価値での買取を提案しました。当事務所は、依頼者側鑑定額を基礎に交渉を進め、最終的に裁判所提示額とほぼ同水準での和解を受諾しました。 - 最終的な履行および解決
和解内容に基づき、会社は依頼者に対して退職慰労金全額と株式譲渡代金を支払い、依頼者は株主としての地位を完全に離脱しました。譲渡承認手続および税務申告手続も当事務所が一括して支援し、実務的整理を完了しました。
結果
最終的に、依頼者は裁判所の和解勧告に基づき、退職慰労金の全額および株式譲渡代金を獲得することができました。当初、会社側が提示していた額面に近い水準とは比較にならない金額での解決が実現しました。
依頼者は、私情に基づく不当解任に対して正当な補償を得るとともに、保有株式の適正評価による売却を通じて完全に会社との関係を整理しました。本件は、経営者排除型紛争において、裁判所が退職慰労金請求と株式買取請求を一体的に処理した実務上の典型例と位置付けられます。