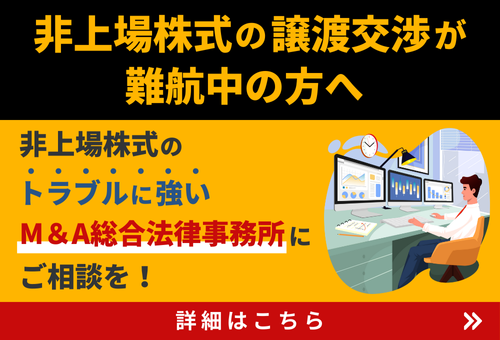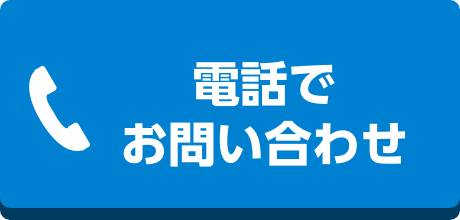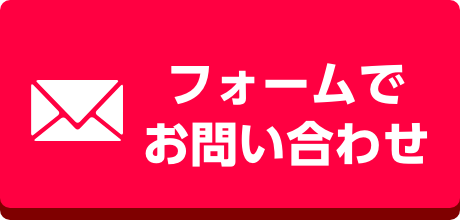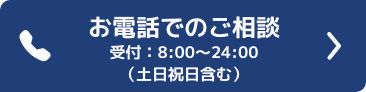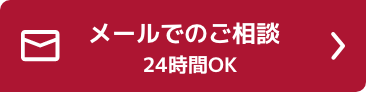非上場株式・少数株式トラブルの解決事例11【長男が会社利益を独占しようと次男を追い出した事例(兄弟間支配争いに伴う株式売却事案)】

事案の概要
依頼者は、地方の老舗製造業会社の創業家の次男であり、長男とともに会社の共同経営にあたっていました。兄弟はともに取締役であり、依頼者も会社発展の中心的役割を果たしていましたが、長男が過半数の株式を保有していたことから、徐々に経営上の発言権が制限されていきました。
長男は会社の支配権を完全に掌握した後、取締役会や株主総会を形式的に運営し、依頼者を実質的に経営から排除しました。さらに、依頼者に対して役員報酬の支払を停止し、会社施設の利用も制限するなど、兄弟間の関係は断絶状態に陥りました。
依頼者は会社の発展に寄与したにもかかわらず、株主としての利益や地位を一方的に奪われ、株式の買取を求めましたが、長男は低額での買い取りを提示し、実質的に拒否しました。依頼者は不当な扱いに強い不満を抱き、当事務所に相談されました。
紛争・主張論点
- 支配株主(長男)が取締役会決議を私物化し、少数株主(次男)を経営から排除した点。
- 会社側(長男)が、株式の買い取りを極端に低い価格(額面近似)で提示した点。
- 依頼者側が、収益還元法およびDCF法に基づき企業価値を評価し、適正価格での買取を求めた点。
- 長男の善管注意義務違反、公私混同行為(会社資産の私的流用、家族への不当給与支給等)の存在。
- 株式買取交渉と訴訟準備を並行して進め、経営支配構造そのものを是正する戦略を採用した点。
当事務所の対応の流れ
- 事実関係の整理および証拠収集
当事務所は、まず依頼者の株主名簿上の地位、役員退任経緯、取締役会議事録、給与支払履歴、会社経費支出明細を精査しました。その結果、長男が取締役会を恣意的に運営し、報酬決定や経費処理を独断で行っていた事実が判明しました。特に、会社資金を私的支出に流用していた点が明確となり、善管注意義務違反が成立する可能性が高いと判断しました。 - 株式買取請求と交渉開始
依頼者代理人として、会社および長男個人に対し正式な株式買取請求を送付しました。長男側は、株式を「兄弟間の内部調整の範囲内」と位置付け、会社法上の手続を軽視する態度をとっていました。提示された買取価格は、会社の簿価純資産を基準にした極めて低額な水準であり、依頼者の主張する企業価値(DCF評価額)の数分の一にとどまりました。 - 私的鑑定の実施と評価書提出
依頼者は公認会計士に依頼し、収益還元法およびDCF法に基づく株式評価書を作成しました。評価では、過去五期の営業利益平均、営業キャッシュフロー、将来成長率をもとに算定した割引現在価値を提示しました。評価書は裁判所での立証資料を見据えた構成とし、会社側の低額提示が不当であることを数値で明確に示しました。 - 長男の不正行為追及および訴訟準備
当事務所は、長男の善管注意義務違反を理由に、損害賠償請求も視野に入れた法的準備を進めました。具体的には、会社資金の私的使用、特定親族への高額給与支給、社用車の個人利用、役員報酬増額決議の欠缺などを整理し、証拠として提出できる形に整備しました。この段階で、長男側は訴訟リスクを強く意識し、交渉テーブルに復帰しました。 - 交渉の進展と最終合意
交渉では、依頼者が提示したDCF法による評価額を基礎に価格協議を行い、会社の資金繰り上の問題から、最終的に長男個人が自己資金で株式を一括買い取る形に整理しました。決済条件は一括支払とされ、会社ではなく長男個人が直接譲受人となりました。
結果
最終的に、依頼者は自らの保有株式を適正に近い価格で売却することができました。当初、長男が提示していた額面に近い水準から比較すると、最終的な売却価格は数倍に上昇しました。
依頼者は、兄弟間の経営関係を完全に清算し、会社経営から離脱することで精神的負担を解消することができました。会社側も、和解により訴訟の長期化を回避できたため、事業継続上の不確定要素を排除する結果となりました。
本件は、同族会社における兄弟間の支配構造対立が法的手続を通じて整理された典型的事例であり、支配株主の専横行為が株主平等原則(会社法第109条)および善管注意義務(同第355条)によって是正された実務的解決例です。