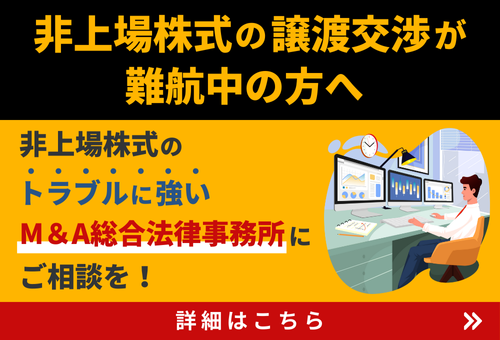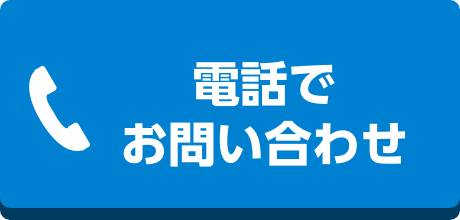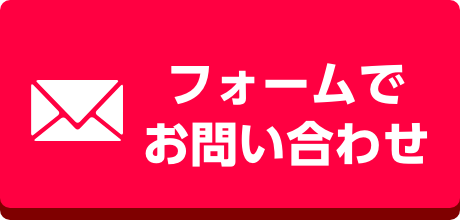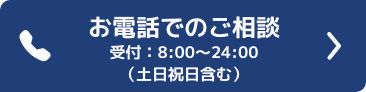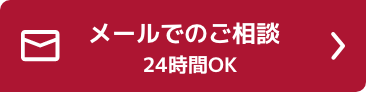非上場株式・少数株式トラブルの解決事例10【会社支配を確立した本家に分家が追い出された事例(同族間支配構造対立に伴う株式売却事案)】

事案の概要
依頼者は、地方の老舗製造業会社の創業家の分家出身であり、かつては取締役として経営に関与していました。依頼者は総発行株式の約二十パーセントを保有しており、長年にわたり会社の経営拡大に寄与してきました。
しかし、会社の実権を握る本家出身の社長は、分家出身の役員や従業員を冷遇し、本家一族による支配を強化する経営方針を採用していました。その結果、分家出身の有力社員や取締役は次々と退職・退任に追い込まれ、依頼者自身も会社から排除されるに至りました。退任後、会社は依頼者に対し配当の支払を停止し、株式の買取にも一切応じない態度を示しました。
依頼者は、会社支配権が本家一族に独占される中で、株主としての権利行使を著しく妨げられたこと、さらに社長が会社資金を私的目的に流用している疑いがあることを重視し、当事務所に相談されました。
紛争・主張論点
- 本家による経営支配強化の中で、分家出身株主が排除された点。
- 社長が配当を停止しつつ自己の役員報酬を不当に増額していた点。
- 社長の善管注意義務違反および会社資産の私的流用の有無。
- 株式買取請求を通じた会社法上の株主保護の適用。
- 株価評価手法としての時価純資産法と収益還元法の併用妥当性。
- 経営支配権を持つ本家側が最終的に株式を取得する形での解決可能性。
当事務所の対応の流れ
- 株主権侵害の整理および法的対応方針の確立
当事務所は、まず依頼者が有する株主権行使の実効性を確認し、配当停止の経緯、取締役会決議の有無、役員報酬決定手続の瑕疵を精査しました。その結果、社長による役員報酬の一方的増額および会社資金の流用に相当する取引が確認され、会社法第355条に基づく善管注意義務違反の疑いが強いと判断しました。 - 株式買取請求および交渉の開始
依頼者代理人として、会社および代表取締役に対し正式な株式買取請求を行いました。会社側は当初、買取に応じず、分家株主である依頼者を事実上無視する対応を続けました。依頼者側では公認会計士に私的鑑定を依頼し、収益還元法およびDCF法に基づく企業価値評価を作成しました。この評価は、会社の継続的利益水準と将来キャッシュフローを基礎としたものであり、配当還元法による低額評価とは一線を画するものでした。 - 訴訟提起および不正行為追及
会社が交渉に応じなかったため、当事務所は株式買取価格決定申立てと並行して、代表取締役の善管注意義務違反を主張する訴訟を提起しました。訴訟においては、社長が配当を停止しながら自らの役員報酬を増額していた事実を指摘し、会社資産の私的流用の疑いを明らかにしました。これにより、会社側も社内外の信用への影響を懸念し、協議の場に応じるようになりました。 - 交渉の進展と裁判所の関与
訴訟手続と並行して裁判所から和解勧告があり、当事務所はこれを踏まえ、会社側と価格条件の交渉を行いました。会社側は当初、時価純資産法による低額評価を主張していましたが、最終的には営業利益を考慮した実勢時価に近い水準を受け入れました。 - 最終合意と履行
最終的に、社長個人が依頼者保有株式を時価に近い価格で買い取る形で和解が成立しました。会社資金による買取ではなく、支配株主である本家当主(社長)自身が資金を拠出し、一括で決済を行いました。株式譲渡承認手続を経て名義書換が完了し、依頼者は保有株式を正式に処分しました。
結果
依頼者は、長年対立していた本家支配構造の中から離脱し、保有株式を公正な価格で売却することができました。当初、会社側は株式を無価値に近い額面水準で評価していましたが、最終的に和解価格は時価評価額に近い水準まで引き上げられました。
依頼者は、株式の売却によって経営関係から完全に離脱し、かつ善管注意義務違反を訴訟上明確に指摘することで、会社経営における公私混同の是正を促す結果となりました。本件は、同族会社における支配株主の行為規制と少数株主保護の双方を実現した実務的解決例といえます。