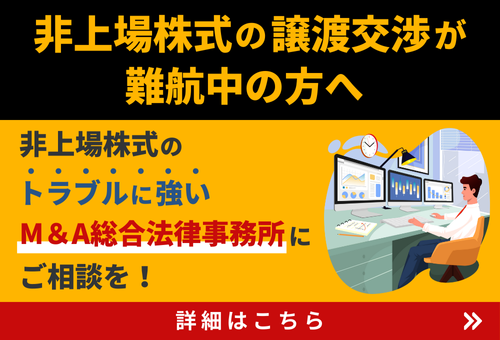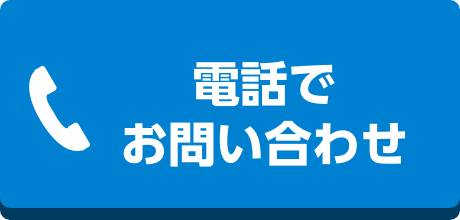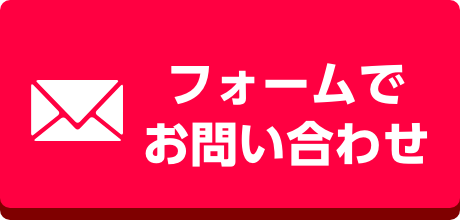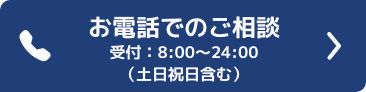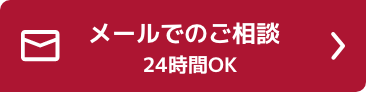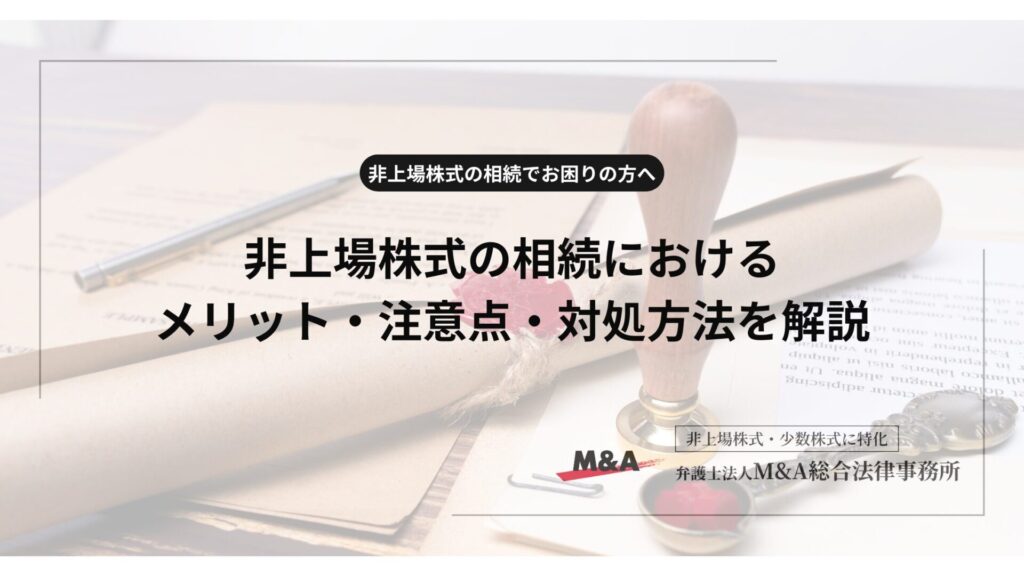
遺産の中に「会社の株式(非上場株式)」があり、相続する際の手続きの流れがわからない。非上場株式を相続することになって「発生したトラブルの解消方法がわからない」という方へ。
非上場株式は市場価格がなく、評価の方法や、譲渡制限会社における譲渡承認・株主名簿の名義書換といった独特のルールがあります。相続税の申告期限は原則10か月。期限に追われる前に、全体像をつかむことが何より大切です。
なお、非上場株式も預貯金や不動産と同じく相続の対象です。譲渡制限が付いた株式であっても、相続は売買のような「譲渡」ではなく権利を引き継ぐ「承継」なので、相続それ自体に会社の承認が必要とは限りません。
ただし、相続人が株主として配当を受け取ったり議決権を行使したりするには、株主名簿の名義書換が欠かせません。
本記事では、まずメリット(経営への関与・配当・現金化の可能性)と注意点(評価が複雑・譲渡制限・情報不足・株主名簿の名義書換の重要性)を整理します。そのうえで、手続きの流れ、評価の考え方、起きやすいトラブル、現金化の選択肢まで、専門用語をかみ砕いて順に解説します。
非上場株式の相続におけるメリットとデメリット(注意点)
非上場株式の相続には、将来に関わるプラス面と、段取り次第で負担が増え得る注意点が存在します。まず得られるメリットを把握しつつ、つまずきやすいポイントを事前に押さえ、期限(相続税は原則10か月)から逆算して進めるための考え方を整理します。
非上場株式を相続するメリット
まずは非上場株式を相続する際のプラス面のメリットを紹介します。
1.経営に関与できる可能性がある
株式を相続すると、株主として株主総会に出席し、議決権を行使できる場合があります。議決権は、取締役の選任や定款変更など会社の重要事項に影響するため、持株が一定割合以上になると意思決定に関わる余地が広がります。
また、一定の持株割合を満たすと、会計帳簿など会社の情報開示を求められる場面もあります。もっとも、議決権が付かない種類株式などでは、同じ「株式」でも権利内容が異なることがあります。
2.配当を受け取れる場合がある
会社に利益が出ていて配当方針が整っていれば、配当金を得られます。非上場株式は配当方針が会社ごとに大きく異なるため、直近の実績と今後の見通しを確認しておくと安心です。相続後の生活設計や納税資金の一部に充当しやすいのもメリットです。
3.株式を売却して現金化できる
非上場株式は会社(自己株式取得)、既存株主、第三者への売却(譲渡)により現金化できる可能性があります。遺産分割で株式を集中させ、他の相続人へは代償金で調整する設計も可能です。納税資金の確保という観点でも重要な選択肢です。
非上場株式を相続するデメリット(注意点)
次に非上場株式を相続する際のマイナス面の注意点を紹介します。
1.相続税の評価が複雑で納税資金が不足しやすい
最大のリスクは、「換金性が低いにもかかわらず、評価額(税金)だけが高くなる」という点です。相続税は超過累進課税で、税率は10%から55%に及びます。内部留保が厚い会社では、評価額が想定以上に高額となり、高い税率が適用される可能性があります。
また、評価方式(類似業種比準価額方式・純資産価額方式等)により評価額が大きく変動します。評価額は高いが現金がないという資金ミスマッチが生じやすい点に注意が必要です。
2.譲渡制限があり非上場株式の売却ハードルが高い
多くの非上場会社では会社の承認が必要です。譲渡承認や価額調整に時間を要し、相続税の申告期限と衝突することがあります。
3.少数株主になると情報が乏しく影響力も小さい
持株が分散すると情報が得にくく、意思決定への関与も限定的になります。
4.株主名簿の名義書換をしないと権利行使や売却が滞る
相続により株式を取得しても、会社に対して株主であることを主張するには、株主名簿への記載が必要です。名義書換が済まないと、配当金の受領や議決権の行使が止まり、売却の手続(譲渡承認の請求など)も進みにくくなります。
5.会社や定款のルールで相続後の選択肢が左右される
会社法174条(売渡し請求)の有無により、保有・売却の選択肢が制限される可能性があります。
相続した非上場株式を売却したい場合はご相談ください
期限に間に合うか不安、交渉が進まない場合は、早めの専門家相談が重要です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、相談実績300件以上を有し、全国対応・オンライン相談にも対応しています。
非上場株式の相続手続きの流れ
非上場株式の相続は、相続人と相続財産の確定→相続する株式の評価→遺産分割方法の合意→株主名簿の名義書換→相続税の申告・納付という順番で進みます。
途中で「売却や買取の検討」「延納・物納などの納税手段の選択」が並走する点が、現金や上場株の相続とは違うところです。申告期限は原則10か月のため、株式評価・株主名簿の名義書換・遺産分割協議を同時並行で動かす段取りが重要です。
| 項目 | 概要 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 1.相続人と財産の確認 | 戸籍で相続人を確定。 被相続人の会社名・持株数・株券の有無を確認し、 株主名簿や定款の条項をチェック。 |
・配当通知・総会招集通知も手掛かり ・定款に「譲渡制限」「売渡請求」条項があるかは要確認 |
| 2.非上場株式の評価算定 | 会社規模(大・中・小)や株主の立場に応じ、 類似業種比準価額方式・純資産価額方式・併用方式・配当還元方式で評価。 |
・株式を評価するための情報が必要 ・評価額は遺産分割や納税計画の出発点 |
| 3.遺産分割協議 | 相続人間で株式の帰属を決定。 株式集中+代償金、売却による換価分割などを検討。 |
・株式は細かく分けにくい財産 ・合意の根拠として評価額と将来計画を共有 |
| 4.株主名簿の名義書換 | 株主名簿に相続人を記載して初めて権利を主張可能。 会社や株主名簿管理人に必要書類を提出。 |
・対抗要件になるため早めに着手 ・会社所定の書式に加え、戸籍/遺産分割協議書/印鑑証明書/株券の有無等も確認 |
| 5.相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内に 申告・納付を行う。 |
・申告要否は基礎控除で確認 ・納税資金が不足すれば延納・物納を検討 ・株式の評価と並行して資金手当てを進める |
1.相続人と相続財産の確認
はじめに、相続人の確定と株式の有無・内容の確認を行います。戸籍一式で法定相続人を確定し、被相続人が保有していた会社名、持株数、株券の有無、株主名簿の記載、定款の該当条項(譲渡制限・相続人等に対する売渡請求など)を確認します。会社から届いている配当金計算書(配当金支払通知書)や株主総会招集通知、議決権行使書面なども手がかりになります。
相続財産の把握は、この後の評価方式の選択に直結します。会社規模(大会社・中会社・小会社)と、取得者が同族株主か少数株主かで評価方法が変わるためです。評価に必要な資料として、直近3期程度の決算書、勘定科目明細、固定資産台帳、借入金の明細、配当の履歴などを揃えておくと、専門家への相談や会社への照会が進めやすくなります。
戸籍収集と株式の存在確認
戸籍で相続人を確定しつつ、会社名や持株数を推定します。株券や過去の配当金計算書、通知類が残っていれば、会社や株主名簿管理人に照会し、名義や持株数をあらためて確認します。
上場株式と調べ方が違う点に注意
上場株式であれば、証券会社の残高報告書を確認したり、証券保管振替機構(株式を電子的に管理する機関)へ照会したりして、保有状況を把握できることがあります。一方で、非上場株式は証券会社や証券保管振替機構で一括管理されていないため、同じ手順では辿り着けません。
手がかりは、株券、株主総会招集通知、配当金計算書、議決権行使書面のほか、確定申告書の控え(配当所得の記載など)です。株券が見当たらない場合でも、株券を発行しない会社もあるので、「株券がない=株がない」とは限りません。会社名が分かったら、株主名簿の管理先(会社または株主名簿管理人)に連絡し、名義と持株数、株券発行の有無を確認します。
株券・定款・株主名簿などの初期収集
定款は譲渡制限や相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)の有無を確認する重要書類です。後者の条項がある会社では、会社が相続を知った日から1年以内に株主総会の特別決議等を経て、相続人に対して売渡しを請求できる局面があります。定款次第で相続後の選択肢が変わるため、早期の精査が必要です。
2.相続する非上場株式の評価算定と方針決定
株式の評価額は、その会社が「大会社」「中会社」「小会社」のいずれに該当するか、また取得者が同族株主か否かによって適用される計算式が異なります。計算式が異なれば、算出される評価額、ひいては相続税額も変動します。
一般的に、類似業種比準価額方式が適用される「大会社」の方が評価額は抑えられやすく、会社の純資産をベースにする純資産価額方式が適用される「小会社」の方が評価額が高くなる傾向にあります。
会社規模(大・中・小)の判定基準
会社規模は、単なる資本金の額ではなく、以下の3つの要素を組み合わせて判定されます。
- 従業員数
- 総資産価額(帳簿価額)
- 直前期末以前1年間の取引金額(売上高)
まず、「従業員数」を確認します。従業員数が70名以上の会社は、資産や売上高に関わらず原則として「大会社」に分類されます。
従業員数が70名未満の場合は、「総資産価額」と「取引金額(売上高)」の規模に応じて、大会社・中会社・小会社の区分を行います。
大会社
取引金額や総資産価額が著しく大きい場合は大会社として扱われ、原則として「類似業種比準価額方式」で評価します。
中会社
中会社は「併用方式(類似業種比準価額方式と純資産価額方式の折衷)」を用います。会社規模が大きいほど類似業種比準価額方式の割合を高く設定でき、評価額を抑えやすくなります。
小会社
原則として「純資産価額方式」で評価します。納税者の選択により併用方式を使用できる場合もあります。
取得者の立場による区分
株式を取得する相続人が「同族株主」か「同族株主以外の株主(少数株主)」かを確認します。
同族株主(経営支配層)
原則的評価方式(類似業種比準価額方式・純資産価額方式等)で評価します。
同族株主以外の株主(少数株主)
経営権を持たない少数株主の場合、配当に着目した配当還元方式が認められる局面があります。
必要資料と準備手順
直近3期の決算書、勘定科目明細、固定資産台帳、借入契約、配当実績、事業概要、主要契約などを時系列で整理します。非営業資産や含み益・含み損の洗い替え、一時的な損益の補正、配当履歴の反映は株式評価額を左右しやすい論点です。評価額の見立てを早めに得られれば、遺産分割や納税資金計画の方向付けが容易になります。
株式評価結果を踏まえた遺産分割の考え方
株式評価額が高い場合は、株式を一人がまとめて取得し他の相続人に代償金を支払う方法や、株式の売却で現金化して配分する換価分割などを検討します。複数人で共有すると意思決定や将来の株式の売却が難しくなりやすいため、誰が保有し続けるかを先に決め、その前提でほかの資産とバランスを取ると遺産分割協議がまとまりやすくなります。
3.遺産分割協議の進め方
遺産分割協議では、株式評価額の前提と根拠を相続人間で共有することがトラブル回避の第一歩です。客観性を高めたい場合は、税理士の評価や第三者評価を用いて「相続税評価」と「売買の目線金額」を切り分けて検討します。相続税評価は税務上の基準であり、株式の譲渡価額(取引価額)と一致しないことがあるため、価格と条件(支払時期・分割払い等)を組み合わせることが有効です。
等価分割の難しさと代償金・換価分割
株式は細かい等分が適しにくい財産です。後継者に集中させて代償金で均衡をとるか、一定割合を売却して換価分割にするか、家計の資金ニーズと会社の安定経営を両立できる線を探ります。
争いを避けるための合意形成
株式評価の根拠、想定する出口(保有・売却・買取請求の可否)、納税方法(現金・延納・物納)を一枚の資料にまとめ、期限(10か月)から逆算したスケジュール表を共有すると合意が前に進みます。
4.株主名簿の名義書換
相続で株式を取得したら、株主名簿の名義書換を行います。相続は一般承継のため、譲渡承認は不要ですが、株主名簿の名義書換が済まないと配当受領や議決権の行使に支障が出ます。会社(または株主名簿管理人)が定める様式に従い、戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続関係説明図等をそろえて申請します。
名義書換で求められやすい添付書類(一般例)
名義書換の書式・添付書類は会社ごとに異なりますが、一般的には次のような資料を求められます。
株券を発行している会社かどうか、遺言で承継するのか遺産分割協議によるのかでも必要書類が変わるため、提出前に会社または株主名簿管理人へ確認してください。
・会社所定の名義書換請求書(株式名義書換請求書など)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
・相続人全員の戸籍謄本(相続関係が確認できる範囲)
・遺言書(ある場合)または遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)
・相続人全員の印鑑証明書(協議書や請求書に実印押印がある場合)
・相続関係説明図
・株券(株券発行会社で、株券を保管している場合)
・名義書換を受ける相続人の本人確認書類(運転免許証など)
会社の承認手続と注意点
第三者へ譲渡する場合は、譲渡制限会社では会社の承認が必要になるのが通常です(承認機関や手順は定款で規定)。一方、定款に相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)の条項がある会社では、相続発生後、所定の手続・決議を経て売渡請求が行われることがあります。定款の有無と承認フロー、相続人等に対する売渡請求条項の有無を名義書換の前後で確認してください。
株主名簿の名義書換が遅れた場合のリスク
名義が旧株主のままだと、配当や議決権の帰属が不明確になり、株式の譲渡手続にも支障が出ます。会社側が株主名簿を基準に権利者を判断する以上、株主名簿の名義書換は早めに着手するのが安全です。
5.非上場株式の相続税の申告・納付
相続税の申告・納付期限は原則10か月。評価や遺産分割が長引きそうでも、期限から逆算して必要書類の整備と納税手段の検討を進めます。現金納付が困難な場合は、延納(許可制・利子税・担保の提供が原則)や、要件を満たすときの物納を検討します。制度の利用には申請期限があるため、評価の見立てが出た段階で税理士と並行検討してください。
相続税の申告が必要かどうかの判断(基礎控除)
相続税は、相続した財産の評価額の合計が一定額を超える場合に申告・納付が必要になります。目安となるのが基礎控除で、金額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
課税価格が基礎控除以下なら、原則として相続税申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、申告を前提とする制度もあるため、非上場株式の評価見込みが出た段階で申告要否を確認してください。
10か月以内に遺産分割がまとまらない場合の対応
遺産分割協議が申告期限までに整わない場合でも、相続税の申告自体は期限内に行う必要があります。
分割未了のまま申告する際は、いったん法定相続分で取得したものとして計算する形が一般的です。未分割だと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割を条件とする制度が使えず、税額が高く出ることがあります。この場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、後日、分割が成立した時点で更正の請求を行い、特例を反映させて税額の調整(還付)を受ける流れがあります。
後継者が株式を承継する場合の納税猶予(事業承継税制)
非上場会社の株式を、会社の経営を引き継ぐ後継者が相続する場合は、一定の要件を満たすことで、その株式に係る相続税の納税を猶予し、後継者の死亡など所定の事由で猶予税額が免除される制度があります(法人版事業承継税制)。株式の評価額が大きく、納税資金が不足しやすい場面では、検討価値のある制度です。
ただし、対象となる会社や株式、後継者の立場に制限があり、認定の取得、相続税の申告期限内の手続、承継後の保有や経営の継続、定期的な報告などが求められます。要件から外れると猶予が取り消されることがあるため、相続が発生した段階で、株式評価や遺産分割と並行して適用可能性を確認してください。
一方で、後継者ではない相続人が単に株式を保有するだけのケースでは、通常は対象になりません。後継者に株式を集中させるか、売却して換価するかも含めて方針を決めます。
期限・必要書類・延納や物納の検討
相続税の延納は、相続税額が10万円超で金銭納付が困難、担保の提供、期限内の申請などの要件を満たす必要があります。物納は管理処分可能な財産に限定され、順位付けや不適格財産の概念があります。いずれも許可制で不備があると却下されうるため、早めの準備が必要です。
納税資金の確保(配当・売却・借入)
納税資金は、配当の活用、会社・既存株主・第三者への株式の売却、金融機関からの借入などを組み合わせて確保します。非上場株式は流動性が低く譲渡承認手続も絡むため、名義書換と並行して会社の意向や売却ルートの可能性を早期に確認しておくと、期限内納付の見通しが立ちやすくなります。
※本サイトの情報は一般的な内容です。税金に関する詳細なご相談や正確な判断が必要な場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
相続税の申告における非上場株式の評価方法
非上場株式には市場価格がないため、相続税の「評価額」は会社の姿と取得する人の立場で決まります。評価額は相続した非上場株式の納税の出発点になるので、まずは「自分のケースはどの方式になりそうか」を掴むことが大切です。
【ポイント】会社規模と株主の立場で評価方式が変わる
非上場株式の評価は、おおまかに次のルールで考えます。
- 大会社「事業の収益力」を重視(類似業種比準価額方式)
- 小会社「持っている資産の中身」を重視(純資産価額方式)
- 中会社は両方のバランス(併用方式[類似業種比準価額方式+純資産価額方式])
同族株主ではない少数株主が相続で取得した場合は、配当実績をもとにした配当還元方式が使われることがあります。
まずは「会社規模」と「同族か少数か」を確認すると、どの方式になりそうか見通せます。
非上場株式の主な評価方式の概要
非上場株式の主な評価方法について紹介します。
類似業種比準価額方式
同じ業界の上場企業データなどを参照し、配当・利益・純資産から相対的に評価する考え方です。会社の業績や配当方針の影響を受けやすく、規模の大きい会社で採用されやすいのが特徴です。
純資産価額方式
会社が保有する資産と負債を洗い出し、資産の中身で評価します。遊休地や多額の現預金など、資産の厚みが評価額に直結します。規模の小さい会社で使われることが多い方式です。
併用方式(類似業種比準価額方式+純資産価額方式)
事業の収益力(類似業種比準価額方式)と資産の厚み(純資産価額方式)の両面を織り込みます。中くらいの会社が対象で、会社の実態をバランスよく反映するイメージです。
配当還元方式(少数株主向け)
同族以外の少数株主が取得した株式に使われる特例的な方式です。過去の配当を基準に計算するため、事業の将来性よりも配当の実績が重視されます。無配でも一定の最低値が出るため、評価額がゼロになるわけではない点には注意が必要です。
【注意点】特例的な会社は「資産重視」になりやすい
保有資産の多くが土地や株式といった資産会社に近いタイプは、原則として純資産を中心に見る取り扱いになります。また、会社を畳む前提に近い状況では、清算価値(解散価額)に近い考え方を使うこともあります。
該当しそうな場合は、一般的な方式と扱いが異なる可能性があると覚えておきましょう。
よくある勘違いと押さえどころ
- 相続税評価額=譲渡価額(取引価額)ではありません。 相続税評価額は“税務上のものさし”で、実際の売買では将来性や支配権の有無なども加味されます。
- 評価方式は選べません。 会社の大きさや株主の立場など、ルールに沿って決まります。
- 無配でも評価はゼロになりません。 配当還元方式には最低の考え方があり、一定の評価は出ます。
- 資料の精度が結果を左右します。 決算書や配当履歴などの基本資料が揃っているかが、評価のブレを小さくします。
※本サイトの情報は一般的な内容です。税金に関する詳細なご相談や正確な判断が必要な場合は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
非上場株式を現金化したい場合や相続したくない場合の対応方法
「納税資金が足りない」
「相続した非上場株式が塩漬けになりそう」
という不安を減らすために、現実的に取り得る3つの方法を紹介します。
相続税の申告・納付期限(原則10か月)を前提に、どの手段が現実的かを先に決めることが重要です。
| 方法 | 概要 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1.遺産分割で他の相続人に引き継ぐ | 自分は株式を持たず、 後継者や特定の相続人に集中させる方法です。 株式を「持つ人」を先に決め、他財産で調整します。 |
・経営の安定を優先できる ・株式を一人に集約しやすい |
・代償金の資金手当が必要 ・共有にすると意思決定が滞りやすい |
| 2.譲渡(売却)して現金化 | 会社・既存株主・第三者の順で買い手を検討し、 価格と支払条件の合意を目指す方法です。 譲渡承認手続が前提になることが多いため、先に手続確認を行います。 |
・納税資金・生活資金を確保できる ・塩漬け株式を回避できる |
・承認手続で時間がかかる可能性 ・相続税評価額と売却価額は一致しない |
| 3.相続放棄 | 株式を含む相続財産全体を承継しない選択肢です。 株式だけを選んで放棄することはできません。 |
・負債やリスクを回避したい場合に有効 ・承継メリットが薄いときに選択肢となる |
・一度放棄するとやり直し困難 ・他の財産も承継できなくなる |
1.遺産分割協議により他の相続人に相続してもらう方法
非上場株式を自分が持たないという選択肢です。
後継者が決まっている家庭や、現金・他財産で調整しやすい場合に向いています。
「株式を誰に集中させるか」だけ先に固めると、協議が進みやすくなります。
はじめに評価の考え方(類似業種比準価額方式・純資産価額方式・配当還元方式のどれに近いか)と
おおよその金額感を家族で共有し、
誰が株式を引き継ぐのが会社や家計に無理がないかを話し合います。
株式は等分しづらい財産のため、
代償金(現金等での調整)や換価分割(売却して現金で分ける)が実務上の調整手段となります。
代償金の原資(預金・保険・借入等)まで含めて設計します。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書に落とし込み、
株主名簿の名義書換まで一気通貫で進めましょう。
名義が変わらない限り、
配当の受領・議決権行使・売却検討はいずれも進みにくくなります。
ポイント
- 後継者・経営の安定を優先できる。
- 合意形成と代償金の資金手当が山場。
- 相続税の期限から逆算し、名義書換まで並行する。
2.非上場株式を譲渡(売却)して現金化する方法
「持ち続けるつもりはない」「納税や生活資金を確保したい」場合は、売却による現金化を検討します。
売却は「価格」だけでなく「支払条件」までセットで詰めることが実務上の要点です。
買い手は
会社(自己株式の取得) → 既存株主 → 第三者
の3ルートです。
どのルートでも「現金の出どころ」を先に確認します。
多くの場合、第三者への譲渡には 会社の承認手続 が必要です。まずは 定款 で譲渡制限の有無を確認し、承認機関(取締役会・株主総会など)、必要書類、所要期間を把握します。期限が決まっている手続もあるため、相続税の申告期限(原則10か月)から逆算して、いつまでに何を揃えるかを先に決めておくと安心です。
譲渡制限株式の場合、第三者への譲渡が承認されないことがあります。会社が譲渡を不承認とするなら、会社が自社で買い取るか、会社が指定する者(指定買取人)が買い取るのが原則です。もっとも、会社の資金事情(分配可能額の範囲など)や社内の決議手続により、買い取りがすぐに進まないこともあります。
また、相続により株主になった人を会社が受け入れたくない場合、定款に「相続人等に対する売渡し請求」の定めが置かれていれば、会社が株式の売渡しを求めることがあります(会社法174条)。請求には株主総会の特別決議が必要で、会社が相続を知った日から1年以内という期限もあります。価格が折り合わない場合は、裁判所の手続により価格が決まることもあります。
このため、売却を前提に動く場合でも、まずは 定款 と 会社の意向 を確認し、承認・買取の見込みとスケジュールを立ててから交渉に入ります。
相続税評価額=売却価額ではありません。
将来収益・支配権・配当方針を加味し、価格と支払条件をセットで調整することが合意への近道です。
ポイント
- 会社→既存株主→第三者の順で現実性を確認。
- 承認手続の長期化に注意。
- 不承認時の買い取り(会社・指定買取人)や、定款の売渡し請求条項(会社法174条)の有無も確認。
- 根拠資料 と 支払条件の調整 をセットで交渉。
3.相続放棄をする方法
相続全体を受け継がない選択肢です。株式だけを放棄することはできません。
預金・不動産等も含めて一体で判断 する必要があります。
相続放棄は、相続開始を知った日から 原則3か月以内 に、家庭裁判所へ申述します。期限を過ぎると、原則として単純承認(相続を受け入れた扱い)となり、放棄できなくなる点に注意が必要です。
また、相続放棄を検討している段階で遺産を処分したり、預金を日常費用以外に使い込んだりすると、放棄が認められないことがあります。まずは財産と負債の全体像を確認し、期限内に判断できるよう準備します。
判断が難しい場合は 限定承認 も検討対象です。限定承認も原則3か月以内に申述が必要で、基本的に相続人全員で手続きを進めます。財産より負債が多い可能性があるものの、全てを放棄するのは避けたい場合に選択肢になります。
ポイント
- 相続放棄は 原則3か月以内 に家庭裁判所へ申述。
- 放棄前の遺産処分や使い込み に注意。
- 迷う場合は 限定承認 も視野に入れる。
非上場株式の相続のお悩みは弁護士がおすすめ
非上場株式の相続は、名義書換、株式評価、会社側の手続が絡むため、期限内に進めるのが難しいことがあります。
たとえば、必要資料が揃わない、会社の回答に時間がかかる、買取条件がまとまらないといった事情で止まりがちです。
相続税の申告期限が近い場合や、会社とのやり取りが必要な場合は、弁護士などに相談すると、進め方と注意点が見えやすくなります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、
非上場株式・少数株式の売却に関する相談実績300件以上を有し、実務に即したアドバイスを提供しております。
全国対応・オンライン相談も可能です。
非上場株式の相続トラブルはご相談ください
非上場株式の相続では、遺産分割、評価、名義書換、会社側の対応が重なり、相続人だけで話が進まないことがあります。株式の評価額で折り合えない、株券や株主名簿の情報が出てこない、会社が譲渡承認や買取に応じないといった場面です。
状況に応じて、名義書換の進め方、会社への照会方法、買取交渉の流れ、裁判所手続の要否を確認しながら進めると、期限超過や紛争の長期化を避けやすくなります。
相続時に起こりやすいトラブル例
- 遺産分割でもめる/株式評価額で折り合えない:誰がどれだけ引き継ぐか、株式の評価をどう見るかで対立しやすい。
- 株式の所在・引渡しで対立:元社長や会社側が株式を開示・引渡ししない、所在が不明などで手続が進まない。
- 遺言や生前の移転をめぐる争い:特定の相続人(社長・後妻の子など)への集中承継、番頭・役員への譲渡主張などで紛糾。
相続後に起きがちな「権利が薄まる」トラブル
非上場会社では、一般の株式とは権利内容が違う株式(種類株式)を発行していることがあります。たとえば、議決権が付かない株式や、株主の属性により権利が変わる株式などです。この場合、相続した後に「株主になったのに議決権がない」「思ったより情報が得られない」と感じることがあります。
また、会社が増資や株式交換などを行うと、持株比率が下がり、議決権割合や売却の進め方に影響することがあります。相続後は、定款の条項、株主名簿の記載、株主総会の招集通知や議案書を確認し、相続した株式の権利内容と最近の変更点を把握しておきましょう。
弁護士へのご相談について
弁護士法人M&A総合法律事務所は、非上場株式・少数株式の売却に関する相談実績が300件以上あり、豊富な経験とノウハウを蓄積しております。ノウハウに基づいて、アドバイスを提供いたします。
まずはお気軽に、弁護士法人M&A総合法律事務所のお問い合わせフォームまたはお電話(サイト記載)からご連絡ください。全国・オンライン/来所にて対応いたします。