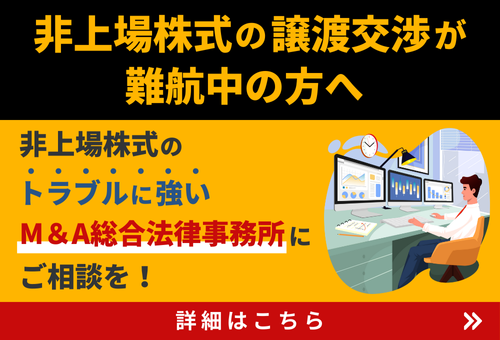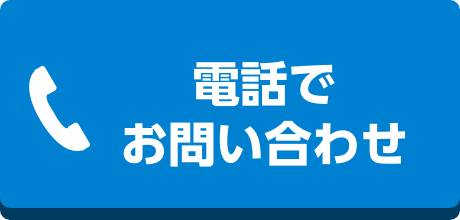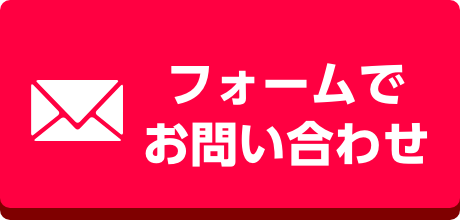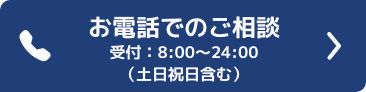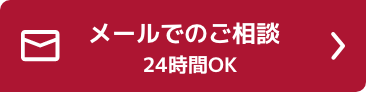お困りではありませんか?
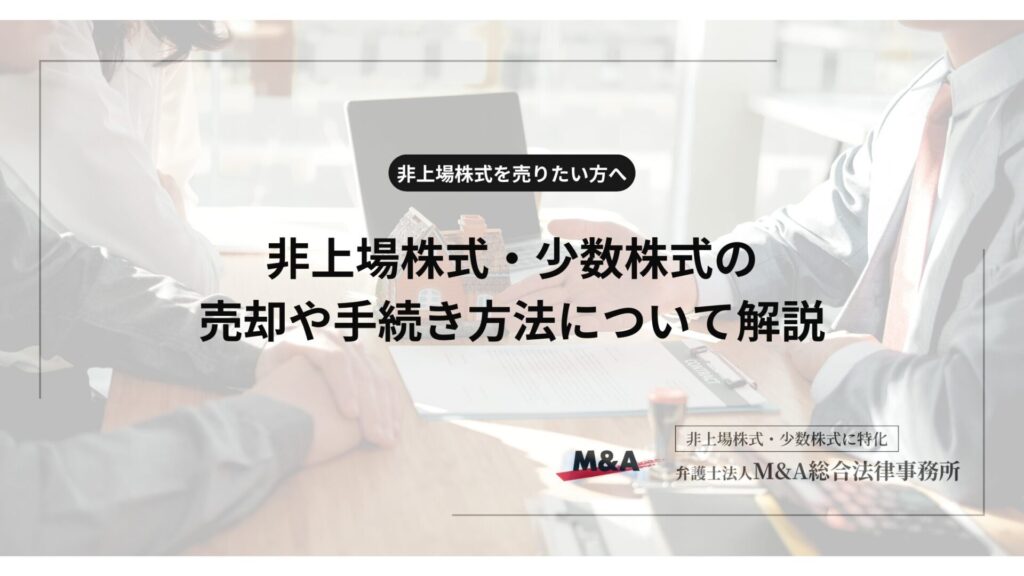
非上場株式・少数株式をお持ちの方の中には、「この株式を売りたいが、本当に売れるのだろうか」という疑問を抱えている方も少なくないでしょう。
結論から申し上げますと、非上場株式の売却や譲渡は可能です。もっとも、非上場株式の売却は、譲渡制限が付されていることが多く、発行会社の承認が必要となる場合が一般的です。譲渡制限がある株式は譲渡制限株式と呼ばれ、定款に譲渡制限の規定が設けられていることが通常です。
上場株式とは異なり、市場で自由に取引できない非上場株式の売却や譲渡には、手続の複雑さ、譲渡制限、税務上の論点など、複数のハードルが存在します。
本記事では、非上場株式・少数株式を売却したいと考えている方に向けて、売却ルート(会社・既存株主・第三者)、注意すべきポイント、および税務上の基本的な整理まで、実務の流れに沿って解説していきます。
非上場株式・少数株式をお持ちの方の中には、「売りたいのに、会社に断られたらどうしよう」「買い手が見つからないのでは」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。相続で引き継いだ株式で、名義や手続きが分からず手が止まっている方もいます。
結論として、非上場株式でも売却・譲渡は可能です。ただし上場株式のように市場で自由に売買できるわけではなく、定款の譲渡制限(会社の承認が必要になる仕組み)や、価格の決め方、税金の扱いなど、確認すべき点がいくつもあります。会社が協議に応じない、著しく低い金額を提示されるといった悩みが出ることもあります。
この記事では、売却先の候補(会社・既存株主・第三者)ごとの進め方と注意点、手続きの流れ、税金の基本を、順を追って解説します。何から始めればよいかを整理し、途中でつまずきやすい場面も含めて見通しを持てるようにします。最後に、早めに弁護士へ相談したほうがよい場面も、具体例とあわせて紹介します。
まず確認したい3つのポイント
・定款に株式の譲渡制限があるか(会社の承認が必要か)
・株主名簿に自分の名義が載っているか(相続後の名義のままになっていないか)
・売却先の方向性(会社に買い取ってもらう/他の株主に売る/第三者に売る)
この3点が分かると、必要書類と手続きの順番が見え、会社とのやり取りも進めやすくなります。
非上場株式の譲渡や売却はできる?上場株式との違い
まずは、非上場株式を譲渡や売却したいと考えた際に押さえておきたい上場株式との違いと、譲渡制限株式の基本を整理します。
非上場株式と上場株式の違い
非上場株式と上場株式の主な違いは以下のとおりです。
| 観点 | 上場株式 | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 流通市場 | 取引所で自由に売買 | 発行会社・既存株主・第三者へ個別交渉 |
| 価格の決まり方(評価方法) | 出来高で価格が即時に可視 | 類似業種比準法・時価純資産法・配当還元法などで算定 |
| 情報開示 | 適時開示・有価証券報告書等が充実 | 開示は任意が中心 |
| 譲渡制限 | 通常なし | 会社承認が必要なことが多い |
| 税務区分 | 上場株式の区分で申告分離課税 | 申告分離課税(概ね20.315%)。上場株式との損益通算は不可 |
1.流通市場の有無
上場株式は証券取引所などの公開市場で自由に売買できますが、非上場株式には市場がありません。発行会社・既存株主・第三者のいずれかに対して、個別に買い手を探し、交渉して合意形成する必要があります。
2.価格の決まり方(評価方法)
上場株式は市場価格が明確です。一方、非上場株式は市場価格が存在しないため、類似業種比準法・時価純資産法・配当還元法などで評価します。どの手法を重く見るかは、会社の規模・事業の継続性・配当実績などの事情により変わります。
3.譲渡制限と承認プロセス(みなし承認)
多くの非上場会社では、定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定めています。承認の判断機関(取締役会か株主総会か)や提出書類は会社ごとに異なるため、まず定款と会社の案内を確認することが大切です。
会社法では、承認請求を受けた会社は原則として2週間以内に承認・不承認を通知する必要があり、通知がない場合は承認されたものとして扱われます(みなし承認)。ただし、請求が会社に到達した日や書類の不備の有無によって、期間の数え方が問題になることもあります。
4.売却ルートと手続の複雑さ
非上場株式の売却ルートは、発行会社への譲渡・既存株主への譲渡・第三者への譲渡に大別されます。どのルートを選ぶかで、必要書類や価格交渉の進め方、承認の要否が変わります。とくに第三者譲渡では、承認が得られない場合に会社や指定買受人による買取に切り替わることもあります。
5.税務区分と損益通算の扱い
個人が非上場株式を売却した場合、譲渡所得はおおむね20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)で申告分離課税となります。
譲渡制限株式とは?
譲渡制限株式とは、会社の定款により株式の譲渡に会社の承認が必要と定められている株式を指します。承認は、取締役会設置会社の場合は取締役会、それ以外の場合は株主総会等で可否を決めます。
この仕組みにより、会社は望ましくない第三者が株主となることを防ぐことができます。ただし、株主が死亡し株式を相続する場合は、原則として譲渡ではなく相続(一般承継)であるため、譲渡制限の直接の対象とはなりません(ただし、定款に相続人等に対する売渡請求がある場合は別途検討が必要です)。
このように、非上場株式の売却は可能ですが、譲渡制限がある株式の売却には、買い手との協議、会社への承認請求、関連書類の提出が必要となり、上場株式と比べて手続が複雑になりやすい点に留意が必要です。
譲渡制限株式の売却を検討される際は、定款・承認機関・所要期間を早期に確認した上で、専門家に相談することをおすすめします。
非上場株式・少数株式の譲渡(売却)時に発生するトラブル
手続の複雑さに加えて、株式譲渡を進めようとした際に予期せぬトラブルが発生することがあります。弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談いただく事案として、以下のようなケースがあります。
- 会社(経営者)が協議に応じないため、売却方針が固まらない。
- 会社に買取を求めたところ、著しく低い買取額を提示された。
- 少数株式を売却したいが、買い手が見つからず、株式を手放せない。
- 譲渡制限を理由に「売却できない」と説明され、手続の見通しが立たない。
非上場株式は、最初の動き方によって、会社との関係がこじれたり手続きの選択肢が狭まったりすることがあります。
連絡の取り方や書類の出し方も結果に影響するため、早い段階で方針を整えることが大切です。
このようなケースでは、非上場株式・少数株式の売却に関する相談実績300件以上の弁護士法人M&A総合法律事務所に、まずはご相談ください。
非上場株式の譲渡や売却のメリットとデメリット・注意点
非上場企業の少数株主として株式を保有する背景はさまざまです。
例えば、相続により株式を取得したものの、経営方針への関与ができない、
あるいは資金化の必要性から売却を検討するケースが少なくありません。
もっとも、非上場株式の売却は、メリットだけでなく固有のリスクや制約も伴います。
そのため、売却を検討する際には、利点と注意点の双方を理解したうえで判断することが重要です。
少数株主が非上場株式を売却するメリット
少数株主が非上場株式を売却することで、主に次のようなメリットが考えられます。
1.まとまった現金を確保できる
非上場株式・少数株式を売却することで、一度に一定額の現金を確保することが可能です。
配当の見込みが乏しい株式を現金化できるため、納税資金・生活資金・他の投資への振替などに柔軟に対応できます。
2.経営リスクや紛争リスクから距離を置ける
少数株主は、会社経営に実質的な影響力を持たない一方で、
株主間対立や経営トラブルに巻き込まれる立場になりやすい側面があります。
株式を売却することで、経営判断や将来リスクから切り離されるという効果があります。
3.相続・事業承継トラブルの回避
非上場株式は相続時
に、相続税負担や遺産分割を巡る対立の原因になりやすい財産です。
生前または早期に売却しておくことで、将来の相続トラブルを回避できる場合があります。
非上場株式・少数株式を売却する際のデメリット・注意点
一方で、非上場株式の売却には、上場株式にはない特有の注意点があります。
1.買い手が見つからない可能性
非上場株式には市場が存在しないため、
売却を希望しても適切な買い手がすぐに見つからないことがあります。
特に譲渡制限がある会社では、売却先が事実上限定される点に注意が必要です。
2.会社側との交渉が長期化しやすい
多くの非上場会社では、株式譲渡に会社の承認が必要となります。
そのため、価格や条件を巡る協議が長期化し、
想定より時間がかかるケースも少なくありません。
事前に定款・承認機関・株主構成を確認しておくことが重要です。
3.株価の適正評価が難しい
非上場株式には市場価格がないため、評価はどうしても専門的判断が必要になります。
評価方法の選択を誤ると、不利な価格で売却してしまうおそれもあります。
税務・法務の観点を踏まえた評価が不可欠です。
さらに、同族会社では、相続による株式分散が経営方針の対立を招くこともあります。
このような場合、後継者への集約を前提とした株式売却が有効な選択肢となることがありますが、
税務上の影響や手続の複雑さも含めて慎重な検討が必要です。
このように、少数株主として非上場株式を保有することには、
明確なメリットと、見落としやすいデメリットの双方が存在します。
売却を検討する際には、早い段階で専門家の助言を受けることが合理的です。
非上場株式の譲渡(売却)までの手続の流れ
非上場株式の売却・譲渡は、上場株式のように市場で取引が完結するものではありません。買い手との話し合いに加えて、会社の承認手続や名義書換など、会社法上の手順を踏む必要があります。
特に譲渡制限がある会社では、承認されるかどうか、承認されなかった場合に会社が買い取るのか、会社が指定する人(指定買取人)が買い取るのか、といった分かれ道が出てきます。さらに、一定の期間内に対応しないと手続きが進みにくくなる場面もあるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。
以下では、非上場株式・少数株式の売却・譲渡の一般的な流れを整理します。
1.会社の情報・定款を調べる
まず、保有株式の基本情報と、会社の制度設計(定款・運用)を確認します。特に次の点が実務上の起点になります。
・株式譲渡制限の有無
定款に株式譲渡制限が設けられているかを確認します。
・株主名簿の確認
ご自身が株主名簿上の株主として登録されているかを確認します。
・議決権比率
保有株式が発行済株式総数の何パーセントに当たるかを把握します(交渉力・価格形成に影響します)。
・会社の財務状況
貸借対照表・損益計算書等から会社の経営状況を概観します(株価算定と交渉方針の基礎資料になります)。
これらは、株式売却交渉と株価算定の出発点となる基礎資料です。
2.株価の相当な評価額を把握する
非上場株式・少数株式には市場価格がないため、相当な株価を算定して交渉の基準を作る必要があります。代表的な枠組みは次のとおりです。
- インカム・アプローチ:将来利益・配当等の見通しを基礎に評価する方法。
- マーケット・アプローチ:類似業種の上場会社や取引事例を参考に評価する方法。
- コスト・アプローチ:会社の純資産(時価純資産等)を基礎に評価する方法。
評価は前提の置き方で結論が変動しやすく、税務・会計・法務の横断的整理が必要になります。
価格交渉に耐える根拠資料を整える観点から、弁護士・税理士・公認会計士等の支援を受けることが合理的です。
3.買い手を探し、交渉する
買い手探索と条件交渉は、非上場株式・少数株式の売却で最も重要な局面の一つです。売却ルートは概ね次の三つに整理できます。
- 株式の発行会社への譲渡:会社が自己株式として買い取る方法。
- 既存株主への譲渡:他の株主に売却する方法。
- 第三者への譲渡:外部の投資家・企業等に売却する方法。
発行会社への譲渡では、会社側提示額が低く、価格交渉が難航することがあります。
まずは、会社が自己株式として買い取る意思があるのか、第三者譲渡を承認する方針があるのかを確認します。
既存株主への譲渡では、持株比率維持の目的で買い手になることがあります。会社によっては、譲渡先や条件を定めた株主間契約が置かれていることもあるため、株主構成や過去の譲渡経緯も併せて確認しておくと実務上安全です。
第三者への譲渡では、買い手探索の窓口(紹介・仲介・候補者)を具体化する必要があります。
ただし、譲渡制限がある場合は会社の承認が前提となるため、承認見込みが不明確なまま進めると、買い手が見つかっても承認されないという事態が起こり得ます。
譲渡制限がある場合は、事前に定款を確認し、承認手続とスケジュールを整理してから交渉に着手することが重要です。
第三者への譲渡を拒否された場合
定款に株式譲渡制限がある会社では、第三者譲渡が承認されないことがあります。
その場合、会社は株式を買い取るか、会社が指定する者(指定買取人)に買い取らせるかを選択します。
会社または指定買取人から「買い取る」と通知された後、売買価格の話し合いがまとまらない場合は、会社法上、通知を受けた日から20日以内に裁判所へ売買価格決定の申立てをすることができます(裁判所に価格を決めてもらう手続きです)。
期間を過ぎると申立てができなくなる場合があるため、通知書やメールなどは保存し、日付も整理しておくと安心です。
4.株式譲渡契約書を作成し、代金決済を行う
株数・価格・支払方法等の条件が固まったら、株式譲渡契約書を作成します。
株式譲渡は口頭でも成立し得ますが、非上場株式では後から認識の相違が生じやすいため、書面化して争点を遮断しておくのが合理的です。
契約書に盛り込みたい項目の例は次のとおりです。
・譲渡対象株式(株式の種類、株数)
・譲渡代金と支払方法
・決済日(代金支払と株式引渡しのタイミング)
・株主名簿の名義書換に必要な書類提出
・解除条件や違約時の取扱い
決済当日は、代金受領と同時に、名義書換請求書等の必要書類を整えます。
株券発行会社では、原則として株券の交付も行います。
5.名義書換と税務対応
株式譲渡が完了したら、会社に対して株主名簿の名義書換を請求し、株主名簿を更新します。
名義書換が未了のままでは、会社から見て株主は旧名義人として扱われ、配当・株主総会招集通知等が旧名義人に送付されることがあります。
会社所定の書類・手続が求められることが多いため、事前に確認しておくと実務が滞りません。
また、株式売却に伴う税務対応も重要です。個人の場合は譲渡所得課税、法人の場合は法人税の対象となり、
自己株式取得等の局面ではみなし配当課税等の論点が生じ得ます。
税務上の取扱いは事案により異なるため、必要に応じて税理士等の専門家と連携して検討することをおすすめします。
非上場株式・少数株式の売却・譲渡は、上記のとおり複数の段階と分岐点を伴います。
スムーズに進めるためには、各ステップで必要資料と期限を整理し、交渉方針と手続方針を並行して設計することが重要です。
非上場株式の価格算定方法と注意点
非上場企業の株式を売却・譲渡する際、株価の算定方法は取引条件や交渉結果に直結します。
非上場株式には市場価格が存在しないため、どの評価方法を採用するかによって評価額が大きく変わる点に注意が必要です。
以下では、実務で用いられる主要な評価アプローチと、その特徴を整理します。
代表的な3つの評価アプローチ
非上場株式の評価方法は、考え方の軸によって次の三つに大別されます。
- コスト・アプローチ:企業の純資産価値を基礎に評価
- インカム・アプローチ:将来の収益・キャッシュフローを基礎に評価
- マーケット・アプローチ:類似企業の市場データや取引事例を基礎に評価
1.コスト・アプローチ
企業の純資産を基準に株式価値を評価する方法です。資産内容が重視される企業や、清算価値を意識する場面で用いられます。
時価純資産法
貸借対照表上の資産・負債を時価評価し、純資産額から株価を算定します。
不動産や有価証券を多く保有する企業では、評価の中心となることがあります。
簿価純資産法
簿価ベースの純資産を用いて評価する方法です。
ただし、簿価と実態価値が乖離している場合には、実情を反映しない可能性があります。
再調達原価法
同種の資産を現在取得すると仮定した場合のコストを基礎に評価します。
設備産業などで補助的に用いられることがあります。
清算価値法
企業を清算した場合に得られる純資産価値を基礎に評価します。
事業継続を前提としない局面で用いられる手法です。
2.インカム・アプローチ
企業が将来生み出す収益力を基礎に企業価値を評価する方法です。事業の継続性が重視されます。
ディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)
将来のキャッシュフローを資本コストで割り引き、現在価値として評価します。
成長性のある企業や、M&A実務で頻繁に用いられます。
収益還元法
将来の収益を一定の還元率で現在価値に換算する方法です。
安定した利益が見込める企業で用いられます。
配当還元法
将来予想される配当額を基礎に株価を算定します。
配当実績や配当方針が明確な企業でなければ適用が難しい点に注意が必要です。
3.マーケット・アプローチ
市場データや取引事例を基準に、相対的に企業価値を評価する方法です。
類似企業比較法
同業種・同規模の上場企業のPER、PBR等を参考に評価します。
類似企業の選定の妥当性が結果を大きく左右します。
取引事例法
過去のM&A取引事例を基礎に評価します。
非上場企業では公表事例が少なく、補助的な位置づけとなることが一般的です。
適正な評価方法を選択するための視点
非上場株式・少数株式の評価は、単一の方法で一義的に決まるものではありません。
以下の事情を踏まえて、相当と考えられる評価方法を選択・組み合わせることが実務上重要です。
・事業の状況
事業継続を前提とする場合はインカム・アプローチ、清算が視野に入る場合はコスト・アプローチが基礎になります。
・資本政策・配当実績
配当実績が乏しい企業では、配当還元法は適さない場合があります。
・市場データの有無
適切な類似企業データが得られる場合はマーケット・アプローチが有効ですが、非上場企業では限界もあります。
評価方法の選択は、交渉戦略や紛争時の主張構成にも影響します。
そのため、税務・会計・法務の観点を踏まえ、専門家と連携して評価を進めることが望ましいでしょう。
非上場株式の売却や譲渡時に気をつけたい税金
非上場株式・少数株式を売却する際の税務上の取扱いは、
個人か法人か、
誰に売却するか(第三者か発行会社か)
によって大きく異なります。
とくにみなし配当課税や損益通算の可否は、事前に整理しておかないと想定外の税負担につながります。
個人が売却する場合の税金
個人が非上場株式を売却した場合、その利益は譲渡所得として扱われ、次の税率が適用されます。
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:所得税額の2.1%
合計税率は20.315%で、申告分離課税となります。
譲渡所得は、
売却代金 −(取得費+譲渡費用)
で計算されます。
損益通算はできるのか
非上場株式の譲渡損益は、上場株式の譲渡損益とは通算できません。
一方で、非上場株式同士の譲渡損益であれば、通算が可能です。
法人が売却する場合の税金
法人が非上場株式を売却した場合、譲渡益は法人の所得となり、法人税等の課税対象になります。税率(実効税率)は会社の規模や所在地、課税所得の金額などで変わりますが、目安として3割前後になることが多いです。
発行会社へ売却する場合の「みなし配当課税」
1.みなし配当とは
株式を発行会社自身に譲渡した場合、実際に配当を受け取っていなくても、
一部が配当を受け取ったものとみなされて課税されます。
これが「みなし配当」です。
2.みなし配当額の計算式
譲渡金額 −(1株当たりの資本金等の額 × 譲渡株式数)= みなし配当額
個人の場合は配当所得、法人の場合は受取配当金として扱われます。
3.譲渡先による課税の違い
- 第三者へ譲渡:取得費+譲渡費用を控除
- 発行会社へ譲渡:資本金等の額 × 株式数を控除
同じ売却でも税負担が変わるため、事前の整理が不可欠です。
4.法人のみなし配当に対する「益金不算入」
法人が受け取るみなし配当には、
法人税法23条(受取配当等の益金不算入)が適用される可能性があります。
| 区分 | 持株比率 | 不算入割合 |
|---|---|---|
| 完全子法人株式等 | 1/3 超 | 100% |
| 関連法人株式等 | 5%以上 1/3未満 | 50% |
| 非支配目的株式等 | 5%未満 | 20% |
例として、持株比率40%の親会社がみなし配当1,000万円を受け取った場合、全額が益金不算入となります。
5.個人のみなし配当は「総合課税」
個人がみなし配当を受け取った場合、
配当所得(総合課税)として扱われ、累進税率が適用されます。
譲渡所得の約20.315%とは課税構造が異なる点に注意が必要です。
6.源泉徴収と確定申告
みなし配当には、支払時に
20.42%(所得税+復興税)
が源泉徴収されます。
原則として、翌年の確定申告が必要です。
7.源泉税を取り戻す「還付申告」
源泉徴収税額が実際の税負担を上回る場合、
還付申告により税金が戻る可能性があります。
- 期限:売却年の翌年1月1日から5年間
- 主な書類:確定申告書B、株式譲渡計算書、源泉徴収明細
- 方法:書面またはe-Tax(e-Taxなら比較的早期に還付)
時価と乖離した売却価格の税務リスク
非上場株式を著しく低い価格で売却すると、
みなし譲渡やみなし贈与として課税されるおそれがあります。
税務上の「適正な時価」
税務上の時価とは、市場価格ではなく、
財産評価基本通達に基づく株式評価額を指します。
売主・買主別の典型的リスク
個人 → 個人
買主に贈与税が課される可能性
個人 → 法人
売主にみなし譲渡所得課税が生じる可能性
法人 → 個人
差額が給与所得や一時所得とされる可能性
売却時期にも注意
売却時期によって、確定申告のタイミングや相続税・贈与税との関係が変わる場合があります。
とくに年末・相続前後の売却では、税務スケジュールを慎重に確認する必要があります。
※本サイトの内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
非上場株式・少数株式の売却・譲渡の事例
非上場株式・少数株式を売却する際には、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
弁護士法人M&A総合法律事務所が関与してきた事例をご紹介します。
事例1:創業家が経営を任せた人物に会社を乗っ取られたケース
依頼者は創業家の元取締役であり、個人で数パーセント、創業家全体では数十パーセントの株式を保有していました。
しかし、創業家全体の組織力が弱かったことから、
株式を安値で売却する者が相次ぎ、創業家全体の株式保有率は徐々に低下しました。
その状況を利用した経営責任者(番頭)が、会社の支配権を掌握しようとしていることが判明しました。
依頼者が自身の株式を会社に売却しようとしたところ、会社は依頼者を一般従業員と同列に扱い、
額面価格での買い取りを提示し、株式の一部所有権すら認めませんでした。
最終的に訴訟・仮処分の申し立てを経て交渉を進め、
裁判所の和解勧告により、
時価純資産価格と収益還元価格を均等に考慮した価格での買い取りが成立しました。
事例2:会社支配を巡り本家が分家を排除したケース
依頼者は創業家の分家出身の元取締役で、20%の株式を保有していました。
退社後、会社から株式の買い取りおよび配当を拒否され、
本家出身の社長による分家出身者の冷遇と排除が進められていました。
社内の支配権は本家に集中し、依頼者も会社から事実上追い出される状況となりました。
依頼者は株式の買い取り請求と同時に、
社長の公私混同による不正を追及。
訴訟と並行した交渉の結果、
最終的に時価に近い価格での株式買い取りが実現しました。
事例3:長男が次男を会社経営から追放し、利益を独占しようとしたケース
依頼者は創業家の次男であり、長男とともに会社経営を行っていました。
しかし、長男が過半数の株式を保有し、
専横的な経営を行った結果、依頼者は役員の地位を喪失しました。
さらに収入を断たれ、自宅からも追い出され、
保有株式については著しく安価な買い取りを迫られました。
依頼者はこれを不服とし、
適正価格での株式買い取りを求めて弁護士に依頼。
長男の公私混同による不正行為を指摘しながら交渉を重ね、
結果的に適正価格での買い取りに成功しました。
事例4:創業者が招聘した外部の社長を私情により解任したケース
依頼者は後継者不在を理由に外部から招聘された社長でした。
しかし、オーナー創業者は依頼者の経営上の意見を不快に感じ、
突然の解任を決定しました。
さらに退職慰労金は支払われず、
株式についても著しく低い価格での買い取りを提示されました。
依頼者は法的措置を講じ、
裁判所の和解勧告により、
退職慰労金全額および
株式譲渡代金の支払いを獲得しました。
※ 実際の当事者や事案の経緯についてはデフォルメしていますので、予めご了承ください。
よくある質問
非上場株式・少数株式を売りたい(譲渡)と考えた際に、多くの方が気にされるポイントをQ&A形式で紹介します。
非上場株式は本当に売れないの?
まず、多くの非上場企業では定款に譲渡制限が設けられており、第三者に譲渡する際には会社の承認が必要となります。
また、取引市場が存在しないため、適正な株価の算定や買い手の探索に時間と労力を要することが一般的です。
もっとも、適切な手順を踏めば株式売却は十分に可能です。
相続で引き継いだ株式もすぐに売れる?
まず、会社の定款に定められた株式譲渡制限の有無や内容を確認する必要があります。
また、会社の経営状況・財務内容、他の株主との関係性も、売却の可否や条件に影響します。
さらに、株式の評価額を適切に算定するためには、専門家による評価が重要となります。
弁護士費用や税金が高くなるのでは?
弁護士費用については、事前に見積もりを取得し、費用対効果を検討することが重要です。
また、株式売却益に対する税金(譲渡所得税など)も考慮する必要があります。
もっとも、適切な手続きを踏むことで、将来的なトラブルを回避し、公正な価格での売却が期待できるため、これらの費用は必要な投資と位置付けることができます。
上場していない株を相続したらどんな対応が必要なのか?
相続人は、相続により承継した旨を会社へ連絡し、株主名簿の書換を請求します。
一方、相続後に第三者へ売却する場合は、多くの会社で定款に基づく譲渡承認が必要になります。
非上場株式・少数株式の譲渡・売却でお悩みの方はご相談ください
非上場株式・少数株式の売却は、適切な知識と専門的ノウハウが求められるため、個人での対応には限界があります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、非上場株式・少数株式の売却に関する相談実績300件以上を有し、実務に即したアドバイスを提供しております。
売却が思うように進まずお悩みの方は、ぜひご相談ください。
お困りではありませんか?